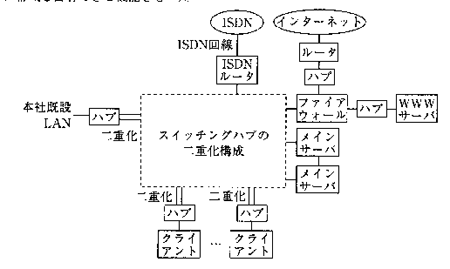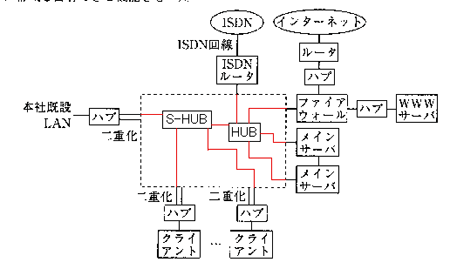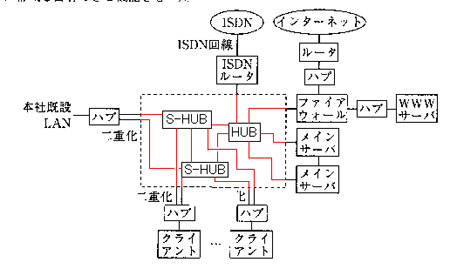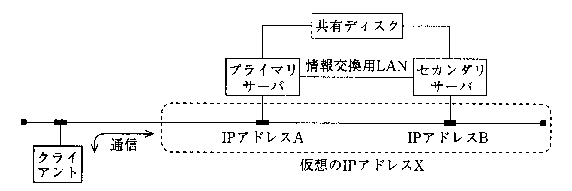| ATMの問題。
☆ ATMについて ☆
ATMは蓄積交換ですが、蓄積交換には3つありました。
|
|
パケット交換 |
・・・ |
ネットワーク層。
戦後間もない頃の技術。
品質は悪いけど、チェックしまくって品質を確保。 |
|
/ |
|
|
|
| 蓄積交換 |
-- |
フレームリレー |
・・・ |
どちらもデータリンク層。
品質がいいのにチェックがあればそれが逆に高速通信の重荷。
冗長ビットを減らした。 |
|
\ |
|
|
|
|
セルリレー |
・・・ |
ATMとは、セルリレーを実現するための一技術ですが、今はこれが100%使用されているので、セルリレーとATMは
同意語と使用されています。が、試験ではこのことを意識しましょう。
☆ ATMとフレームリレーの違い ☆
フレームリレーのフレームはMAX1500バイトに対して、ATMのセルは53バイトとかなり小さいです。
蓄積交換はみんなが使うので、高速道路、回線交換は占有して使うので鉄道と考えられます。
ここで、フレームリレーはたくさん運べるのでトラック、セルリレーは少ししか運べないので車と考えましょう。
ダンボールを50個運んでみます。
フレームリレーは1回でドン!と運べて効率は良いのですが、ATMは50に分けて運ばなくてはならず、効率が悪いです。
では、なぜこんなんがあるんでしょう?
セルリレーはマルチメディア(映像とか音声)用の技術です。
50バイトのデータ(映像とか音声)を1秒で送れるとしますと、
フレームリレーは1フレームMAX1500バイトですから、送り終えるのに30秒掛かります。
セルリレーは48バイト、48バイト・・・と送れるので、1秒ごとに細切れで送れます。
フレームリレーでは、相手側に30秒後に届いて、チェックして再生します。・・・30秒経たないと返事が出来ない
セルリレーでは、1秒ごとにデータが来て再生できます。・・・遅延が小さい。
また、セル、フレームが欠けた時の影響度合いが違います。
1秒分の映像が欠けてもごまかせますけど、30秒では無理ですよね?
フレームリレーではFCSでのチェック機能はありますが、ATMはチェック機能はありません。リアルタイムを重視しています。
☆☆☆ QoS (Quality of Service)
☆☆☆
 QoSにはカテゴリとして4つあります。 QoSにはカテゴリとして4つあります。 ・CBR(Constant
Bit Rate)
・VBR(Variable Bit Rate)
これは rt-VBR(リアルタイムVBR)とnrt-VBR(ノンリアルタイムVBR)に分かれます。
・ABR(Aberable Bit Rate) あと番外編として、UBR( Unspecified
Bit Rate 無指定)があります。 ☆
このCBR、VBR、ABRについて FRは速度が変動しました。
| 0 |
CIR |
 アクセス回線速度 アクセス回線速度 |
| |--- |
-|- |
-------| |
ATMでのFRでいうところのCIR
(ATMでは別の言い方があります)の設定によってこのように分かれます。
CBR
(ギャランティ) |
 アクセス回線速度=CIR アクセス回線速度=CIR |
VBR
(ふつうのFR) |
0 < CIR <  アクセス回線速度 アクセス回線速度
|
ABR
(ベストエフォート) |
0 = CIR |
CBRでは、共有なのに確実に アクセス回線速度を出すことが出来ます。 アクセス回線速度を出すことが出来ます。 では、なぜ、高速速度なのに確実に着くといえるのでしょうか? CBRでは高速道路を専用道路にしています。
(「名神高速道路はあなたのものです」、「信号も全部青にして下さい」と言ってるようなものです) B-ISDNがそれに該当します。(B:Broadband
広帯域) 専用道路にすると言いましたが、一生ではなくデータを通す時だけ占有します。 (これをゴア副大統領はスーパーハイウェイと言いました) ☆
で、残りのUBR ATMはマルチメディア用の通信です。  テレビ会議のようなリアルタイム性重視ではCBR, テレビ会議のようなリアルタイム性重視ではCBR,
一時間後でもいいようなものはABR(CBRではもったいない)がいいです。 こういう時は、用途に合わせて、何回線も契約するんでしょうか? それとも、一番高いCBRで契約するんでしょうか? UBRでは用途に合わせて切替えることが出来ます。 |
設問1
本文中の【 a 】~【 d 】に入れる適切な字句を答えよ。
| aはゆらぎ、ジッタでいいでしょう。
bは説明しましたように QoSです。 QoSです。
cは
| ネットワーク層 |
↑上位層 |
| データリンク層 |
AALレイヤ・・・ATMアダプテーションレイヤ(セルの分解、組立) |
| ATMレイヤ ・・・ セルの転送 |
| 物理層 |
|
ここで問題です。
パケット交換では
パケットの交換、組立はPADと言いました。
では、フレームリレー、セルリレーでは何と言いますか?
フレームリレー・・・FRAD、 セルリレー・・・CLAD
です。
dはマイナすぎる問題なので、知らなくてもいいです。
|
(解答)
[a]=ゆらぎ [b]= QoS
QoS
[
c ] =
ATMアダプテーション
[d]=同期
設問2
ATM伝送における伝送効率に関する次の問いに答えよ。
計算問題です。計算ミスに注意しましょう。有効数字、単位、切り上げか?四捨五入か?
気をつけましょう!あとで検算できるように、紙の隅に使った数字と単位を残しておきましょう。 |
(1)U社提案書第3項のプロトコルタイプ5において、ユーザデータ長が250バイトの
場合のセル数を求めよ。
250バイト
ユーザデータ |
8バイト
トレーラ |
30バイト
空白 |
| 288バイト(48バイトの整数倍) |
6セルですね。
|
(解答)
6セル
(2)(1)の場合の伝送効率が何%になるかを求めよ。答えは小数以下を四捨五入して整数
で求めよ。ここで、伝送効率はセル中に占めるユーザデータの割合とする。
| ユーザデータの割合ですから、分子は250バイトになります。
250 / ((5+48) × 6) × 100 = 78.61
丸め、有効数字、単位のチェックはOKですか?
単位:%、有効数字:小数以下を四捨五入して整数
79%
|
(解答)
79%
設問3
計算問題です。計算ミスに注意しましょう。有効数字、単位、切り上げか?四捨五入か?
気をつけましょう!あとで検算できるように、紙の隅に使った数字と単位を残しておきましょう。 |
大阪支店向けプリント出力時のセル送出速度を求めよ。ここで、プリント出力の転送
を固定ビットレートと考え、セル中に占めるユーザデータを47バイトとせよ。セル送出
速度は、毎秒送出できる最大セル数とする。答えは小数以下を切り上げて整数で求めよ。
|
CBRです。
384kビット/秒 / 53 × 8 バイト/セル =
905.6セル/秒
丸め、有効数字、単位のチェックはOKですか?
単位:セル数、有効数字:小数以下を切り上げて整数
設問2(2)は四捨五入でした。今回は切り上げです。同じ問題で丸め方が違うので注意しましょう。
906セル/秒
☆ 同期 ☆
ここで、同じデータリンク層のCSMA/CDは連続転送出来ませんでした。
IFG(フレーム間隔) 12バイトとPA(プリアンブル)
8バイトがフレーム間で必要になります。
ATMは連続転送できます。
ATMは非同期、CSMA/CDはプリアンブルでフレームごとに同期をとっています。
ATMは毎回毎回同期をとりません。最初だけとります。
☆ 1セル=何バイト? ☆
セルは誰が何と言おうが
ユーザデータは1バイトでも45バイトでも今回のように47バイトでもペーロードは48バイトです。 |
(解答)
906セル
設問4
T君とU社技術担当者の打合せにおいて、U社技術担当者から" HDLCフレームの送
HDLCフレームの送
出後の応答監視タイマ値を、場合によっては変更しないと通信がうまくいかないケース
もあります"と言われた理由を60字以内で述べよ。
・何を問われてるかをしっかり確認しましょう。(何を問われているかにマーキング!)
理由を問われています。
ホストは時間にシビアです。
時間以内に返ってこなかったらダメです。
TDMをATMにすると、応答時間が遅くなる可能性がある・・・ようなことを言っています。
これを書くとしましょう。
それはなぜか?
CBRは速度一定です。データが達するのは保証します。
しかし、ATMはFCSを持っていません。
もし、上位のプロトコルで見たらエラーがあったら、再送などしなければなりません。
それで、遅くなる可能性があります。
※
なぜ遅れるか・・・まで追求するとすごく難しいです。
iTAC流に6,7点を狙いましょう。
|
(解答)
TDMからATMに替えると応答時間が遅くなり、応答監視タイマ値を越える可能性があるため。(45)
なぜかまで書くと、TDMからATMに替えるとエラーによる再送など、応答時間が遅くなり応答監視タイマ値を越える可能性があるため。(55)
設問1
本文中の【 a 】~ 【 d 】に入れる適切な字句又は数値を答えよ。
| 呼損率の問題です。
aはアクセスサーバか集合TAのどちらかです。
アクセスサーバは1~7層全てですが、集合TAは物理層なので答えはアクセスサーバでいいでしょう。
bはすぐ上に、
>パソコンについては、他業務に利用できるので小売業者の負担
と書いています。これもそれでいいでしょう。
(本来の業務以外で使う可能性があるということです)
cは”呼損率”です。
呼=call、呼量、呼損率、アーランB式は回線交換ならではの言葉です。
その中で重要になってくるのが呼損(話中だった)です。
ダイヤルしたのに掛からなかった。その行為が損・・・これが語源です。
つまり、呼損率は話中だった率です。
小売業者:
ピークの呼量は
1000台 × 2 × 0.2 × 360秒 / (60 × 60)秒 = 40アーラン
・・・ c
卸売業者:
ピークの呼量は
50 × 6 × 0.2 × 600秒 / ( 60 × 60) 秒 = 10アーラン ・・・
これは本文に書いてます。
ここで問題です。
呼損率の表から小売業者と卸売業者の呼損率を
0.001、0.003、0.01、0.03、0.1とした時の
回線本数を求めてください。
解)
| 呼損率 |
小売業者
40アーラン |
卸売業者
10アーラン |
| 0.001 |
※ |
21 |
| 0.003 |
※ |
20 |
| 0.01 |
※ |
18 |
| 0.03 |
48 |
16 |
| 0.1 |
42 |
13 |
※表中にデータなし
今回は小売業者が呼損率0.03、卸売業者が0.1なので、回線数はそれぞれ48回線(本文中に書いてます)、
13回線(d)です。 |
(解答)
[a]=アクセスサーバ [b]=他業務に利用
[c]=40 [d]=13
設問2
本文では小売業者用センタ側回線と、卸売業者用センタ側回線を別々なものとして、
Bチヤネル数を計算している。しかし、両回線を共用し、小売業者も卸売業者も一つの
代表番号にダイヤルして、先着順にBチヤネルを利用する仕組みにすることができる。
このようなセンタ側回線の共用に関する次の問いに答えよ。
代表番号の場合はあらかじめ何本か契約しておきます。
| xxx-xxxx |
--- |
xxxx |
|
|- |
xxxx |
|
|- |
xxxx |
|
|- |
xxxx |
|
|- |
xxxx |
|
|- |
xxxx |
|
(1)回線の共用によって話中となる確率が低くなるか、回線数の削減によって月額使用
料を低くできるかのいずれかの効果が見込まれ、検討する価値が十分にある。このよ
うな効果が見込まれる理由を、本文に即して、30字以内で述べよ。
| 回線を共用することによって、48本と13本で合計61本用意します。
これにより、話中の確率が低くなるか?
回線数が削減できるか?です。
1日の時系列を見ると、ピークはずれています。両方合わせたピークは
10アーラン+40アーラン=50アーランでは無いと推定できます。
これを回答にすればいいでしょう。 |
(解答)
ピークがずれているので、合計値も下がり、回線数も削減できる。(28)
(2)(1)の検討のために、何を調査する必要があるか。30字以内で述べよ。
| これはあくまでも推定です。
時系列に追いかけて、グラフに書けば設計は出来るわけです。 |
(解答)
各時間あたりの小売業者と卸売業者のトラフィック量(24)
設問3
受発注システムの費用に関する次の問いに答えよ。
(1)小売業者が受発注システムを利用する場合の月額費用を、次の①~③を前提にして
求めよ。
計算問題です。計算ミスに注意しましょう。有効数字、単位、切り上げか?四捨五入か?
気をつけましょう!あとで検算できるように、紙の隅に使った数字と単位を残しておきましょう。 |
① この小売業者とGセンタは別市内にあり、その間の距離は25kmとする。
②1か月に20日、土日を除く平日に、Bチヤネルを一つ利用する。
③ 回線接続装置は買取りでないものとする。
| ②に平日と書いてますが、平日にも昼間、夜間、深夜があります。
>サービス時間帯は9時~19時である。
ですから、昼間です。
③で買取ではないですから、レンタルです。
月額使用料ですから、付表5+付表6です。
基本使用料は、3630+60+1700=5390円。
通信量は、
↑ 360 秒 / 45 秒 ↑ × 10円 = 80円
80円 × 2アクセス/日 × 20日 = 3200円
5390円 + 3200円 = 8590円 |
(解答)
8590円
(2)本文では受発注システムの構築、運用に関する費用について述べているが、すべて
の費用項目を挙げているわけではない。本文で記述していないが、発生すると見込ま
れる通信関係の費用は何か。二つ挙げ、それぞれ20字以内で述べよ。
| これにはいろんな考え方があります。
付表4にあります新規契約(イニシャルコスト)や、ISDNの工事費などもそれに該当するでしょう。 |
(解答)
・新規契約料(5)
・工事費(3)
設問4
小売業者の利用促進策についてH君は、月々発生するISDNの費用を安くして、小売
業者の費用負担を軽減する案を検討した。その具体策を20字以内で述べよ。ただし、
ISDNサービスの利用は変更しないものとする。
| 本文にあるように、ISDNの費用を小売業者負担にしたら使ってくれなくなった。
安くすれば使ってくれるかな?
バルク転送にすれば、通信時間は短くなるけど料金は高くなります。
要は、全体的に高くなっても小売業者負担が安くなればいいのです。
・フリーダイヤルにする・・・通信費3200円は卸売業者になり、小売業者負担は無くなります。
・割引サービスを使う
・回線接続装置(DSU)を買取にする・・・レンタル料(1700+60)が無くなります。
・コールバック
他に
>ほとんどが東京、大阪近郊に分布している。
で、アクセスサーバは東京にしかありませんから、アクセスポイントを大阪に増設すれば、
大阪の小売業者の通信費は安くなるでしょう。
あと、画像データは軽くしてもいいですね。 |
(解答)
フリーダイヤルにする(10)など
| これは、アナログ専用線からフレームリレーへのリプレースの問題です。 |
設問1
本文中の【 a 】~【 d 】に入れる適切な字句を答えよ。
 HDLC-NRMは HDLC-NRMは
・半二重、相手の許可無しでは送れない。
・一次局、二次局に分かれている。
です。
ホスト、端末間ではホストが送信権を持っています。
端末から出したくても送信権が無いので出せません。
ですから、ホストは「何か用は無いですか?」とポーリングを出して送信権を渡します。
それで、用が無ければ端末はそのまま送信権をホストに返します。
---
a:送信権の制御、あと状態監視の制御でいいでしょう。
b:ゲートウェイの先にあるのは・・・アナログ専用回線、あとモデムです。
c;FR網
d:Q.933はLMI(PVC状態監視)です。これは平成9年午後2問2の表の注意書きに書いてたことです。
(1年前には注意書きしてくれてたものが、穴埋めに出てきます。) |
(解答)
[a]:送信権or状態監視
[b]:アナログ専用回線orモデム [c]:FR網 [d]:LMI or
PVC状態監視
| 最後の追込みを控えて・・・
TCP/IP、CSMA/CD、フレームリレー、セキュリティの問題は毎年出ています。
TCP/IP、CSMA/CDについてはずっとやってきましたのでいいでしょう。
フレームリレー、セキュリティについては、効率的にやっておいて下さい。
過去から追っかけてみてください。問題は進化していっています。 |
設問2
図2のセンタにおける構成を破線内に図示することで完成させよ。ただし、機器や配
線の種類は本文に出てくるものに限定し、図に用いる記号も本文にあるものを使用せよ。
| FR網の両側にはTAが必要です。
TAの向こう側にはR( ルータ)が必要です。 ルータ)が必要です。
これで、CSMA/CDになります。
これに、GWを挟めばOKでしょう。
GWと ルータはクロスケーブルで直結できますが、HUBを使えばストレートケーブルでつなぐことが出来ます。 ルータはクロスケーブルで直結できますが、HUBを使えばストレートケーブルでつなぐことが出来ます。 |
(解答)
| [ホスト] |
--- |
[ GW ] |
--- |
[ R ] |
--- |
[ TA ] |
--- |
( FR網 ) |
設問3
アナログ専用線利用の場合、GWが応答を返せない状態になったときに、ホストで実
行されるポーリングの再試行処理に関する次の問いに答えよ。
|
ホストのGWに対するポーリングに関する設定は、次のとおりである。
・正常な場合のポーリング間隔は0.2秒である。
・ポーリングタイムアウトは1.0秒である。
・タイムアウトが発生した場合の再試行処理は、次の手順で行う。
① 再試行を3回まで行う。
② その後、7.0秒の間隔をおいて、再びポーリングを行う。これがタイムアウトになる
と、①を行う。
③ もう一度②を行う。
④ ③まで実行しても応答がないと、ホストは障害とみなす。
ですから、
|
回数 |
時間 |
| ポーリング→タイムアウト |
1 |
1.0 |
| ① |
3 |
3×1.0=3.0 |
| ② |
1 |
7.0+1.0=8.0 |
| ① |
3 |
3×1.0=3.0 |
| ② |
1 |
7.0+1.0=8.0 |
| ① |
3 |
3×1.0=3.0 |
| 障害 |
|
|
| 合計 |
12回 |
26秒 |
|
(1)ホストで障害を検知するまでに、ポーリングが何回連続してタイムアウトになるか
を求めよ。
(解答)
12回
(2)ホストで障害を検知するのに最低何秒掛かるかを求めよ。
(解答)
26秒
設問4
表中の【 e 】~【 g 】に入れる適切な字句を、【 e 】、【 f 】についてそれぞ
れ30字以内、【 g 】について10字以内で答えよ。
| e
前橋事業所のPCはGWがホストと思っています。
そのGWを移動しました。当然のことながら、PCのGWのIPアドレスの設定を変えてやる必要があります。
f
| ホスト |
|
GW |
|
R |
|
TA |
|
| ・----- |
------- |
-・- |
--- |
-・- |
--- |
-・- |
----- |
|
HDLC
NRM |
|
|
|
|
|
FR網 |
何で障害を検出しますか?LMIで検出します。
g
現状よりも速くなるでしょう。9600bps→CIR16kbpsですから。 |
(解答)
[e]:PCのGWのIPアドレスの設定を変更する(20)
[f]:LMIで検出する。(8)
[g]:現状よりも速くなる(9)
設問5
あなたがY君の立場で検討した場合、どちらの案を選択するか。理由も含めて30字以
内で述べよ。
・何を問われてるかをしっかり確認しましょう。(何を問われているかにマーキング!)
選択を問われています。
あなたならどっち? 午後2的な問題です。
ホストとGW間は短い方がいいので案2の方がいい。など。
30字なので必要なことだけでいいです。
|
(解答)
ホストとGW間は短い方がいいので、案2を選択する。(25)
設問1
貨物追跡情報システムに関する次の問いに答えよ。
(1)本システムでは貨物の配送状況が追跡できない箇所がある。追跡できないために発
生する問題点を二つ挙げ、それぞれ30字以内で述べよ。
・何を問われてるかをしっかり確認しましょう。(何を問われているかにマーキング!)
問題点を問われています。
この問題は追跡できない場所を問われているのではありません。注意しましょう。
追跡情報の一番最初の入力と一番最後の入力はどこでしょう?
支店から支店まです。
これより前もこれより先も追跡できません。
それでどうなるでしょう?
問題点を問われているので回答は暗いイメージで書いてください。
|
(解答)
契約運送店が集荷したことがわからない。(18)
契約運送店が配送したかがわからない。(17)
(2)(1)の問題点をD社が独自に解決する方法を、70字以内で述べよ。
・何を問われてるかをしっかり確認しましょう。(何を問われているかにマーキング!)
独自に解決する方法を問われています。
D社独自にです。契約運送店がではありません。
①、⑧をやってもらえばいいので、
携帯端末を契約運送店に貸し与えて、バーコードラベルを印刷してもらえばいいでしょう。
|
(解答)
契約運送店が携帯端末を貸し与え、貨物情報の入力、付属プリンタでバーコードラベルを
印刷して貨物に貼ってもらう。配達時にもバーコードリーダで読み取ってもらう。(70)
設問2
本社増設LAN二重化構成に関する次の問いに答えよ。
(1)図3のスイッチングハブの二重化構成を、スイッチングハブ2台、ハブ1台を用い
て完成させよ。ただし、ハブの方がスイッチングハブよりも故障率が十分に低いもの
として、全体で信頼性の高い二重化構成を検討すること。
| 図示問題です。
信頼性向上のための問題です。
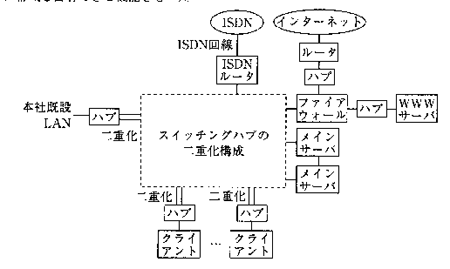
二重化されていないのは信頼性の高いHUBに、二重化されているものの一方をスイッチングHUBに接続しましょう。
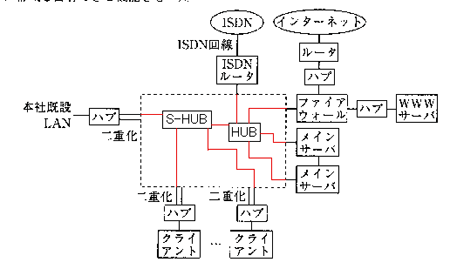
で、残りの一方をS-HUBにつなぎます。
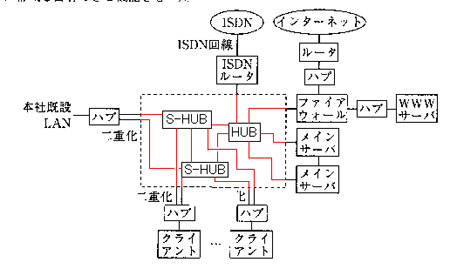
メインサーバは2つありますが、これはS-HUB2つで二重化しなくていいのでしょうか?
メインサーバ2台は独立して動きますので、HUBにつないだ方が信頼性が高いでしょう。 |
(解答)
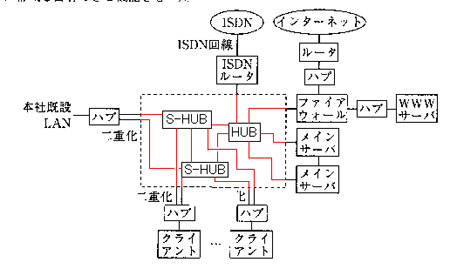
(2)(1)の構成を可能にするために、スイッチングハブがもつべき機能を答えよ。
(解答)
スパニングツリー
設問3
メインサーバの二重化構成に関する次の問いに答えよ。
(1)本文中の【 a 】~【 g 】に入れる適切な字句を答えよ。ただし、【 c 】~
【 f 】には、図4の用語又は記号を用いよ。
| a,b
2重化方式には3つあります。
温かい(ウォームスタンバイ)と、熱いと冷たいです。
→コールドスタンバイとホットスタンバイ
コールドスタンバイじゃ故障してから電源を入れます。そして、OSを上げてバックアップファイルをLOADします。
・・・MTTRが長い
ホットスタンバイは常に同じ作業をしています。メモリ、ディスクの内容全て一致しています。
ですから、故障してもすぐに切り替わります。
・・・MTTRは0
その中間がウォームスタンバイです。
電源が入っていて、OSが入った状態でスタンバイしています。(熱くもなく、冷たくもなく、、、)
c
これはx(エックス)です。いいですね。
d,e
両方プライマリです。この試験は同じ記号を2度使ってはならないことはありません。
g
ARPキャッシュ、ARPテーブル、ARPテーブルキャッシュ、でいいでしょう。
ここで、プライマリサーバとセカンダリサーバについて
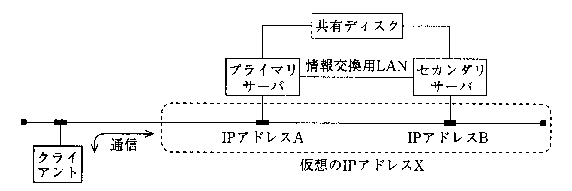
プライマリサーバとセカンダリサーバ、どっちに信頼性が高いのを置くでしょう?
TCP/IPから見れば、どっちがメインでしょう?主導権を握っているでしょう?
セカンダリはプライマリに生存確認(ヘルスチェック)を行います。
クライアントから見れば、プライマリがメインですけど、セカンダリは影武者のように裏で仕切っています。
ですから、プライマリに性能を高くしますが、信頼性はセカンダリの方を高くします。 |
(解答)
[a][c]
コールドスタンバイ、ホットスタンバイ
[d] プライマリ
[e] プライマリ
[f] セカンダリ
[g] ARPキャッシュ
(2)メインサーバと同一セグメントに設置されたクライアントは、メインサーバからの
通知で接続先サーバの切替処理を行う。 ルータを介してほかのセグメントに設置され
ルータを介してほかのセグメントに設置され
たクライアントでも、サーバ切替えのためにはこの処理が必要か不要か、解答欄のい
ずれかを○印で囲め。また、その理由を60字以内で述べよ。
・何を問われてるかをしっかり確認しましょう。(何を問われているかにマーキング!)
必要か不要と理由を問われています。
不要です。
 ルータを越えるということは、ネットワークが変わるということなので、ARPでの返答は ルータを越えるということは、ネットワークが変わるということなので、ARPでの返答は ルータが知っていればいい ルータが知っていればいい
|
(解答)
 ルータを越えるとネットワークが変わる。接続先サーバが切り替わったことは
ルータを越えるとネットワークが変わる。接続先サーバが切り替わったことは ルータが知っていればいいため。(50)
ルータが知っていればいいため。(50)
設問4
システム導入作業方法に関する次の問いに答えよ。
(1)全国の支店への導入作業を開始する前に、本社とそれに近接した一つの支店への導
入作業を同時期に実施した。この順序と方法で最初の導入を実施した理由を二つ挙げ、
それぞれ35字以内で述べよ。
・何を問われてるかをしっかり確認しましょう。(何を問われているかにマーキング!)
理由を問われています。
順序で一つ、方法で一つ書いてみましょう。
順序については、一度に全支店に配布するんじゃなくて、1つやってから全部やったということです。
これをパイロットモデル、テストケースと言って、
まず、ここで問題点が洗い出されます。注意点、対策が洗い出されます。手順書の見直しも出来ます。
リハーサルです。
方法は、まず近場を選んだということです。
問題発生時には、対応が迅速に出来ます。 |
(解答)
・1支店だけ導入することで、注意点を洗い出し、手順書見直しが出来るため。(34)
・近場から導入することで、問題発生時には対応が迅速に行えるため。(30)
(2)現地作業を効率的に行うために、導入機器に対して事前に実施しておくべきことを、
45字以内で述べよ。
・何を問われてるかをしっかり確認しましょう。(何を問われているかにマーキング!)
事前に実施しておくべきことを問われています。
こういう問題はまず、新規設置なのか、設定変更なのかを考えます。
新規の場合は、模擬的な動作確認と、新規の設定を行う必要があります。 |
(解答)
機器の新規設定を行い、作動しているかを模擬的にテストを行い、確認しておく(36)
(3)導入後直ちに試験運用に移るために、各支店のシステム利用者に対して事前に行っ
ておくべきことは何か。20字以内で述べよ。
・何を問われてるかをしっかり確認しましょう。(何を問われているかにマーキング!)
事前に行っておくべきことを問われています。
これは 運用管理の定番問題です。 運用管理の定番問題です。
問題点は 運用管理者がいない、スキル不足です。 運用管理者がいない、スキル不足です。
対策は、教育とマニュアルです。 |
(解答)
教育し、マニュアルを作成、配布しておく(19)
設問5
システムの 運用管理に関する次の問いに答えよ。
運用管理に関する次の問いに答えよ。
(1)システム導入の初期段階で、最も必要となる 運用管理システムの機能を答えよ。ま
運用管理システムの機能を答えよ。ま
た、その理由を60字以内で述べよ。
・何を問われてるかをしっかり確認しましょう。(何を問われているかにマーキング!)
理由を問われています。
 運用管理システムの機能は3つありました。 運用管理システムの機能は3つありました。
>(1)ソフトウェア配布
>(2)リモート操作
>(3)稼動監視
3つ共重要です。ですから、理由がしっかりしていれば正解になります。
初期段階で(導入してすぐ)・・・がキーワードです。
ソフトウエア→バグが多くて安定しない。
リモート操作→操作に不慣れによるトラブルが予想されます。
リモート操作で説明できます。
稼動監視→思わぬパケットが飛び交ってるかもしれません。
練習ですので、全てについて回答を作ってみましょう。 |
((Tomの)解答)
<ソフトウエア配布>
運用初期段階ではソフトウエアもたくさんのバグを抱えていると思われ、
修正、再配が頻繁に行われるため(51)
<リモート操作>
運用初期段階では、ユーザはソフトの操作方法が不慣れなので、
この機能でユーザに対して遠隔で説明が出来るため(53)
<稼動監視>
運用初期段階ではネットワーク内に思わぬパケットが飛び交ってる恐れがあるため、
監視し、対策を行う必要があるため(55)
(2)メイン管理サーバからのソフトウェア配布は、複数のサブ管理サーバに対して同時
に行われる。D社のネットワーク構成でソフトウェア配布を行う場合、特に注意すべ
きことを35字以内で述べよ。
・何を問われてるかをしっかり確認しましょう。(何を問われているかにマーキング!)
注意すべきことを問われています。
解決法ではありませんので注意してください。
何に注意をするのでしょう?前提は方式Bです。
キーワードは同時に・・・です。
支店の数は150ヶ所
支店と本社の間はISDNです。
ISDN30回線 →
Bチャネル1回線2本使ったとしても60チャネルです。同時転送は無理です。
で、何を注意しましょう?
日常は業務でも使ってます。それを圧迫しないかな?
|
(解答)
ネットワークは日常業務にも使っているので、それを圧迫しないか注意する(34)
(3)D社の場合、ソフトウェア配布は方式Bが適しているとしたが、方式Aの利点も考
えられる。方式Aの利点を25字以内で述べよ。また、その利点を生かせるソフトウェ
ア配布方法と、それがD社に適していない理由を、それぞれ60字以内で述べよ。
・何を問われてるかをしっかり確認しましょう。(何を問われているかにマーキング!)
利点と配布方法とD社に適していない理由を問われています。
利点は、一度に150ヶ所送らなくていいことです。本社ネットワークに関する負荷が大変楽になります。
配布方法は全国を地域ごとにブロック分けして、その中心のサーバに転送し、サブサーバは階層リストにより、
それぞれのサブサーバに転送すればいいでしょう。
適していない理由は、中継すると回線が一つしかないので負担はサブ管理サーバの方に行ってしまう。
またそれにより、設定が増えるが、 運用管理を任せられる担当者がいないのも問題です。 運用管理を任せられる担当者がいないのも問題です。 |
(解答)
<利点>
本社ネットワークに関する負担が軽減する点(20)
<配布方法>
全国を地域ごとにブロック分けして、その中心のサーバに転送し、サーバは階層リストにより、
それぞれのサブサーバに転送する(60)
<適していない理由>
回線が1つしか無いためサブ管理サーバに負担がかかり、またそれにより設定が増えるが、
 運用管理を任せられないため。(54)
運用管理を任せられないため。(54)
設問6
システム導入作業時に発生した問題と解決策に関する次の問いに答えよ。
(1)ISDN回線が接続されたままになった原因は、支店あてのパケットが定期的に流れ
たからである。このパケットはどのような機能をもっているか。また、この問題を解
決するためにどのような対応をしたと想定できるか。それぞれ30字以内で述べよ。
・何を問われてるかをしっかり確認しましょう。(何を問われているかにマーキング!)
機能とどのような対応をしたと想定できるかを問われています。
>このパケットは、メイン管理サーバから発行されていた
>ので、稼働状況監視のタイミングの見直しを行うとともに、また別の手段でネットワ
>ークの状態変化を早期に発見するための機能を働かせることで対応した。
これについての問題です。
メイン管理サーバから出ています。 ルータからではありません。
ルーティング情報と答えたら×です。 ルータからではありません。
ルーティング情報と答えたら×です。
メイン管理
サーバ |
|
|
|
○----- |
-----[ R ] -----[ R ] ----- |
-----○ |
 SNMP SNMP
マネージャー |
|
SMNP
エージェント |
MIB(Management Information Base)情報とは SNMPのデータベースです。 SNMPのデータベースです。
機能はMIB情報の収集を行うためのパケットです。
まず、対策として10秒間隔やったものを10分おきにしたら従量課金なので安くなるといったものです。
別の手段で・・・です。
 SNMPの中にTrap機能というのがあります。 SNMPの中にTrap機能というのがあります。
エージェントにしきい値を設定しておいて、それを越えたらエージェントからマネージャーに知らせる機能です。
(平成11年 午前問30)
これで対応したのでしょう。
リクエストを出す必要が無いですから、対策1+対策2合わせ技で使えます。マスタリングTCP/IP
P.255熟読のこと |
(2)ARP要求パケットに対する二つの応答は、プロキシARP機能が発行したものであ
った。これが発生した原因を30字以内で述べよ。
本来なら、例えば ルータに聞けば ルータに聞けば ルータが答えてくれます。 ルータが答えてくれます。
プロキシARPはでしゃばりです。問われたら、でしゃばり君も答えます。
本文中の一部の機器に設定の違い・・・とは?
設定ミスで同じIPアドレスが2つ存在したので、両方から異なるMACアドレスが返ってきたのです。
こちらの解説は変更しました。
テクニカルエンジニア(ネットワーク)過去問 平成10年 午後2 問1 解説
(Tomの解答例)
クライアントのサブネットアドレス設定変更をし忘れたため(27)
|