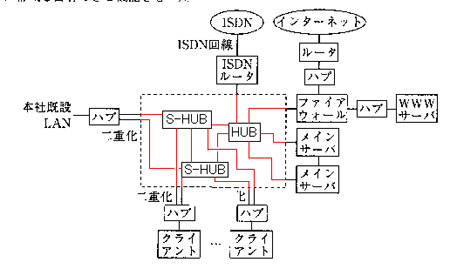|
設問1
貨物追跡情報システムに関する次の問いに答えよ。
(1)本システムでは貨物の配送状況が追跡できない箇所がある。追跡できないために発
生する問題点を二つ挙げ、それぞれ30字以内で述べよ。
何を問われているかにチェック!
問題点です。追跡できない箇所ではありませんので注意しましょう。
でも、解く順番としてはまず、追跡できない箇所の洗い出しです。
本システムを探してみましょう。
図1の○付き数字(①~⑧)が無いところです。
(a)最初に支店に届くまで
(b)支店または契約配送店を出たあと
この2箇所です。
それぞれについて、問題点を書いてあげたらいいですね。
最近、クロネコヤマトの宅急便でも同じようなサービスをやっています。
もし、同じようなことがあれば、困ることを書いてあげればいいのではないでしょうか。
|
(Tomの解答例)
①までの契約配送店に着送、①に
発送されたことを確認できない点(30)
荷物が⑧のあと契約配送店に着送、
発送されたことを確認できない点(30)
(2)(1)の問題点をD社が独自に解決する方法を、70字以内で述べよ。
じゃあ、どうするか?ですね。
70字ですから相当ゆっくり書けそうです。
携帯端末を契約配送店に渡して、
・配送時は貨物情報を入力し、付属のプリンタでバーコードラベルを印刷して貨物
に貼付させる
・配達時は貼付されたラベルを携帯型バーコードリーダで読み取らす。
です。
これで完璧ですね。
|
(Tomの解答例)
携帯端末を契約配送店に渡し、配送時は貨物情報を入力し、ラベル
を印刷し、貨物に貼付。配達時は貼付されたラベルをバーコードリ
ーダで読み取らす。(69)
設問2
本社増設LAN二重化構成に関する次の問いに答えよ。
(1)図3の スイッチングハブの二重化構成を、 スイッチングハブの二重化構成を、 スイッチングハブ2台、ハブ1台を用い スイッチングハブ2台、ハブ1台を用い
て完成させよ。ただし、ハブの方が スイッチングハブよりも故障率が十分に低いもの スイッチングハブよりも故障率が十分に低いもの
として、全体で信頼性の高い二重化構成を検討すること。
条件として、
(a)switch × 2, Hub × 1
(b)Hubの故障率 << switchの故障率
(イ)まずは、Hubから2本出てる所は、素直にそれぞれswitchを付けて上げましょう
(ロ)ISDN ルータと ルータと ファイアウォールは、switchとHubどっちかに付けてあげないと ファイアウォールは、switchとHubどっちかに付けてあげないと
いけないんですけど、(b)の条件からHubの方がいいですね。
(ハ)メインサーバは悩むところなんですが、本文を読んでいると、
片方はウォームアップです。ですから、それぞれswitchよりも、
両方Hubの方がいいような気がします。
(ニ)最後にHubから線を2本出し、それぞれのswitchに付けるとOKですね。 |
(Tomの解答例)
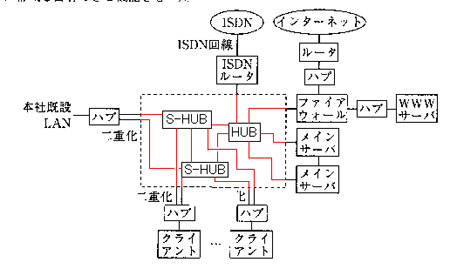
(2)(1)の構成を可能にするために、 スイッチングハブがもつべき機能を答えよ。 スイッチングハブがもつべき機能を答えよ。
これは定番の問題ですね。
(1)の回答を見てみると分かりますが、見事にループ構造です。
一つパケットを投げてしまうと、メルトダウンを起してしまいますね。
その辺りは NW塾Sコース6回目
にて解説していますので、見てください。
答えは、スパニングツリー機能ですね。
|
(Tomの解答例)
スパニングツリー機能
設問3
メインサーバの二重化構成に関する次の問いに答えよ。
(1)本文中の【 a 】~【 g 】に入れる適切な字句を答えよ。ただし、【 c 】~
【 f 】には、図4の用語又は記号を用いよ。
用語問題ですね。
さらに”ただし”書きに注意しましょう
>信頼性を高めるために図4の二重化構成とする。二重化方式は、
>一般に【 a 】、ウォームスタンパイ、【 b 】の3方式
これはコンピュータシステムの分野ですね。
信頼性向上(冗長)技術
冷たい、暖かい、熱いです。
コールドスタンバイ、ウォームスタンバイ、ホットスタンバイ。
分野が違うので、深い内容は割愛します。
>今回提案する方式では、2台のサーバで仮想のIPアドレスを共有させることによって、
>メインサーバが切り替わったことをクライアントのアプリケーションプログラムに意識
>させないようにできる。メインサーバとクライアントの通信、及びメインサーバの切替
>えは、次の方法で行われる。
>① メインサーバと通信を行うとき、クライアントはIPアドレス【 c 】に対して、
> MACアドレスの取得を行う。
>② 【 d 】サーバが応答し、クライアントはメインサーバとの通信が可能になる。
>③ プライマリサーバとセカンダリサーバ間は情報交換用LANで相互に接続されてお
> り、常時互いの生存を確認する。
>④ 【 e 】サーバに障害が発生したとき、【 f 】サーバはこれを検知してサーバが
> 設置されているLAN上の機器に通知する。
>⑤クライアントは、メインサーバからの通知を基にクライアントがもつ【 g 】を書
> き換え、IPアドレス【 c 】とMACアドレスとの対応関係を変更する。
これをまとめます。
① クライアント => メインサーバ 通信時: メインサーバのIPアドレスは?
これは何となく分かりますね。きっとXでしょう。
② 何も問題なければプライマリサーバが立ち上がるはずです。
③ プライマリサーバ
<=> セカンダリサーバで「生きてる」ことの情報交換
④ プライマリサーバが死んだら、セカンダリサーバが検知して、LANに教えてやる
⑤ ARPテーブルを書き換える
| ARPテーブル |
| |
IP アドレス |
MAC アドレス |
| ★プライマリサーバ正常時 |
X |
プライマリサーバのMACアドレス |
| ★プライマリサーバ故障時 |
X |
セカンダリサーバのMACアドレス |
|
(Tomの解答例)
【 a 】:コールドスタンバイ
【 b 】:ホットスタンバイ a,bは順不同
【 c 】:X
【 d 】:プライマリ
【 e 】:プライマリ
【 f 】:セカンダリ
【 g 】:ARPテーブル
(2)メインサーバと同一セグメントに設置されたクライアントは、メインサーバからの
通知で接続先サーバの切替処理を行う。 ルータを介してほかのセグメントに設置され ルータを介してほかのセグメントに設置され
たクライアントでも、サーバ切替えのためにはこの処理が必要か不要か、解答欄のい
ずれかを○印で囲め。また、その理由を60字以内で述べよ。
何を問われているかにチェック!
必要か、不要か? とその理由です。
まずは、同一セグメントか、 ルータを越えているかで何が違うでしょう? ルータを越えているかで何が違うでしょう?
=>ネットワークが違いますね。
次にARPでの名前解決ですが、IPアドレスからMACアドレスを問い合わせる時に、
・同一ネットワーク
・別ネットワーク
これの違いは何だったでしょう?
同一ネットワーク : 問合せ対象の機器がMACアドレスを返す。
別ネットワーク :  ルータが自身のMACアドレスを返す。 ルータが自身のMACアドレスを返す。
つまり、別ネットワークの場合、たとえサーバが切り替わっても、 ルータ自身のMACアドレスに関しては ルータ自身のMACアドレスに関しては
何も影響は無いので、処理は不要ですね。
処理が必要なのは、サーバのセグメントに接続されている ルータです。 ルータです。
|
(Tomの解答例)
不要に○印
別ネットワークの場合、ARPの対象は ルータであり、サーバの切 ルータであり、サーバの切
替わりは、 ルータ自身のMACアドレスに影響が無いため(56) ルータ自身のMACアドレスに影響が無いため(56)
設問4
システム導入作業方法に関する次の問いに答えよ。
(1)全国の支店への導入作業を開始する前に、本社とそれに近接した一つの支店への導
入作業を同時期に実施した。この順序と方法で最初の導入を実施した理由を二つ挙げ、
それぞれ35字以内で述べよ。
何を問われているかにチェック!理由を問われています。
>この順序と方法で最初の導入を実施した
理由なので、
・本社に近接した支店で導入作業を実施した理由
・一つの支店で導入作業を実施した理由
この2つで回答を作ってみましょう。
なぜ、本社に近接した支店で導入作業を行ったんでしょう?
東京に本社があって、横浜、大阪どっちの支店で導入確認をするか?って感じです
ね。
もし大阪で導入確認しようとすると、大阪までの電車賃が掛かります。
さらに、もし問題が発生し、本社の応援が必要な場合は、さらに電車賃が掛かりま
すし、
それ以上に新幹線で移動しても3時間は掛かっちゃいますね。
もし横浜なら1時間も掛かりません。
その辺を書いてあげればいいでしょう。
近傍の方が問題発生時、本社から
すぐに対応、移動コストもかから
ないため(34)
あと、1つの支店のみで作業を行った理由です。
近いからといって、横浜、新宿、浦和、千葉などを同時に実施しちゃったら
どうなるかですね。
こういう場合は問題が発生するとすれば同じ内容です。
プログラムミスとかサーバの設定指示ミスとか、、、。
同じ問題に対して、全てに対応するのなら、1つで十分確認して、
徐々に拡大した方がいいですよね。
複数同時に導入作業を行うと、共
通の問題発生時、全支店で対応を
要するため。(35)
|
(Tomの解答例)
近傍の方が問題発生時、本社から
すぐに対応、移動コストもかから
ないため(34)
複数同時に導入作業を行うと、共
通の問題発生時、全支店で対応を
要するため。(35)
(2)現地作業を効率的に行うために、導入機器に対して事前に実施しておくべきことを、
45字以内で述べよ。
何を問われているかにチェック!実施しておくことです。
マニュアル作成とか、手順書作成のような対人ではなく、導入機器に対して
ですので注意しましょう。
どんな機器を導入するでしょう? 図6を見ると、サブ管理サーバですね。
ではサブ管理サーバの機能は?
ソフトウエア配布機能、リモート操作機能、稼動監視機能。。。
この機能の導入は”事前”というより、”本番”ですね。
そのいざ本番をやる時のことをイメージしましょう。
「じゃあ、今から始めます!」と本社から指示を受け、
ネットワークの設定が出来ていなかったら? ケーブルが繋がってなかったら?
怒られますよね?
|
(Tomの解答例)
導入機器のネットワーク設定をし
通信確認をする。また、必要ソフ
トのインストールも完了しておく(45)
(3)導入後直ちに試験運用に移るために、各支店のシステム利用者に対して事前に行っ
ておくべきことは何か。20字以内で述べよ。
| そして、こっちは対人です。
これは定番の「教育」、「マニュアル作り」ですね。
|
(Tomの解答例)
マニュアルを作成し、利用者に教育すること(20)
設問5
システムの 運用管理に関する次の問いに答えよ。 運用管理に関する次の問いに答えよ。
(1)システム導入の初期段階で、最も必要となる 運用管理システムの機能を答えよ。ま 運用管理システムの機能を答えよ。ま
た、その理由を60字以内で述べよ。
| 何を問われているかにチェック! 機能とその理由を問われています。
”初期段階""最も必要となる"もキーワードですね。
この 運用管理システムの管理機能は何だったでしょうか? 運用管理システムの管理機能は何だったでしょうか?
3つありましたね。
(1)ソフト配布機能
(2)リモート操作機能
(3)稼動監視機能
最初は(3)だと考えました。最初なんて、正常に稼動しないものですから。。。
でも、じっくり考えると全部とても必要なんですね。
もちろん、作問者の意図というものもあるでしょうが、どの機能を選んであげても、
60文字で理由の筋が通っていればいいようなな気がします。
それぞれについて、書いてみましょう。
|
(Tomの解答例)
1)ソフト配布機能の場合
導入前のテストでは発見されなかったバグも
実際に導入すると発見されることがよくある。
その場合に迅速に対応できるため。(56)
2)リモート操作の場合
導入初期段階では、トラブル発生しやすいが、
簡単なトラブルでは、リモート操作で対応す
ることが有効な手段となるため。(54)
3)稼動監視機能の場合
導入初期段階では特に稼動状態が安定せず、
トラブルの発見が遅れると、復旧にも時間
を要するため。(46)
(2)メイン管理サーバからのソフトウェア配布は、複数のサブ管理サーバに対して同時
に行われる。D社のネットワーク構成でソフトウェア配布を行う場合、特に注意すべ
きことを35字以内で述べよ。
何を問われているかにチェック!注意すべきことを問われています。
対策を問われていませんので注意しましょう。
”D社のネットワーク構成で”と書かれていますので、図6を見ます。
方式Aと方式Bがありました。D社はどっちの方式を採用しましたか?
>今回のケースでは、方式Bが適していると判断した。
ですね。
方式A:途中のサブ管理サーバで中継して配布先のサブ管理サーバに配布する方式、
方式B:直接配布先のサブ管理サーバに配布する方式
方式Aでは、本社が配布するのは数支社分だけです。
方式Bでは? 本文の最初に書いてあります。
>全国150か所に支店又は中継店をもつ。
150ヶ所に同時にソフトウエアを配布します。WAN回線は? ISDNです。
帯域に注意する必要がありそうです。
|
(Tomの解答例)
ソフトを直接同時に配布するため、ISDN
回線の帯域不足に注意すべき。(33)
(3)D社の場合、ソフトウェア配布は方式Bが適しているとしたが、方式Aの利点も考
えられる。方式Aの利点を25字以内で述べよ。また、その利点を生かせるソフトウェ
ア配布方法と、それがD社に適していない理由を、それぞれ60字以内で述べよ。
先ほど比較しましたね。
(2)の逆が方式Aの利点になります。
利点は
本社のメイン管理サーバ、管理者の負担が軽減できる点(25)
これしかないでしょう。
で、次はこの方式を生かせる配布方法です。
ちょっと考えてしまいますね。
で、先にそれがD社に適していない理由を考えてみました。
それが分かれば、配布方法も見えてくると思います。
D社に適していない理由:
トラブルが発生時、復旧させる管理者が支店
にいないため、その下流の支店全てに影響を
及ぼすため。(45)
ってことは、もしトラブルが発生しても、対処できる技術者が
支店にいれば出来る配布方法を考えてあげればいいです。
<配布方法>
全国を地域ごとにブロック分けして、その中
心のサーバに転送し、サーバは階層リストに
より、それぞれのサブサーバに転送する(58)
|
(Tomの解答例)
利点
本社のメイン管理サーバ、管理者の負担が軽減できる点(25)
配布方法
全国を地域ごとにブロック分けして、その中
心のサーバに転送し、サーバは階層リストに
より、それぞれのサブサーバに転送する(58)
D社に適していない理由
トラブルが発生時、復旧させる管理者が支店
にいないため、その下流の支店全てに影響を
及ぼすため。(45)
設問6
システム導入作業時に発生した問題と解決策に関する次の問いに答えよ。
(1)ISDN回線が接続されたままになった原因は、支店あてのパケットが定期的に流れ
たからである。このパケットはどのような機能をもっているか。また、この問題を解
決するためにどのような対応をしたと想定できるか。それぞれ30字以内で述べよ。
・何を問われてるかをしっかり確認しましょう。(何を問われているかにマーキング!)
機能とどのような対応をしたと想定できるかを問われています。
>このパケットは、メイン管理サーバから発行されていた
>ので、稼働状況監視のタイミングの見直しを行うとともに、また別の手段でネットワ
>ークの状態変化を早期に発見するための機能を働かせることで対応した。
これについての問題です。
メイン管理サーバから出ています。 ルータからではありません。 ルーティング情 ルータからではありません。 ルーティング情
報と答えたら×です。
SMNP (Simple Management Network Protocol)には5つの
がありました。
メイン管理
サーバ
○----- -----[ R ] -----[ R ] ----- -----○
 SNMP
SMNP SNMP
SMNP
マネージャー
エージェント
①Get Request
---------------------------------->
②Get Response
<----------------------------------
③Get-Next Request
---------------------------------->
④Set Request
---------------------------------->
⑤Trap
<----------------------------------
MIB (Management Information Base)情報とは SNMPのデータベースです。 SNMPのデータベースです。
機能はMIB情報の収集を行うためのパケットです。
まず、対策として10秒間隔やったものを10分おきにしたら従量課金なので
安くなるといったものです。定期的に流れていたパケットは①のGet
Requestでしょう。
機能としては、
サーバからエージェントに対し、定期的に稼
動状態を確認する機能
でいいでしょう。次にどのように対応したかです。
①の監視間隔を長くしたのと別の手段で・・・です。
 SNMPの中にTrap機能というのがあります。 SNMPの中にTrap機能というのがあります。
これは、エージェントにしきい値を設定しておいて、それを越えたらエージェント
からマネージャー
に知らせる機能です。
|
(Tomの解答例)
機能
サーバからエージェントに対し、定期的に稼
動状態を確認する機能(30) ---
CHANGE 02/9/23
対処方法
通知するしきい値を高くし、通知
しにくくして通信量を抑える。(29)
(2)ARP要求パケットに対する二つの応答は、プロキシARP機能が発行したものであ
った。これが発生した原因を30字以内で述べよ。
この設問に対して、初めはこのようなアプローチをしました。
プロキシARP機能を搭載している ルータでは、「このIPアドレスに対する要求が来た場合、 ルータでは、「このIPアドレスに対する要求が来た場合、
自分の ルータのMACアドレスを返すんですよ~」と設定します。 ルータのMACアドレスを返すんですよ~」と設定します。
例:COMSTARZ ROUTER 詳細設定マニュアル/プロキシARP設定ページ
このIPアドレスの設定を既存LAN側の ルータで誤った?というのが ルータで誤った?というのが
自分の回答のアプローチでした。
回答したノード:
1つめ:サブサーバ
2つめ:既存LAN側の ルータ ルータ
確かに、このアプローチだと、「同一セグメントで正常に接続できるものもあった」
という本文が成立しないですね。
答えは別にありますね。
本文中の図2にアドレスを書き込むと以下のようになると思います.
なお,本文中より既設LANと増設LANの境界はハブであり,
また,もともと172.17.0.0と172.16.0.0を相互に接続していたことから
その間に ルータがあることが考えられます. ルータがあることが考えられます.
※クライアントAのアドレス,支店のネットワークアドレス
およびサブサーバのアドレスは適当につけました.
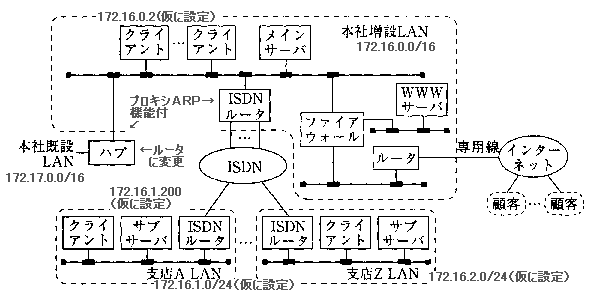
この状況で本社既設LANのクライアントAからサブサーバ172.16.1.200にARP要求を
送ったとします.
設定が正常の場合は、
ネットマスクによりネットワークアドレスが異なることがわかります.
そうするとISDN ルータAのIPアドレス宛をあて先に設定しARP要求をブロードキャストします. ルータAのIPアドレス宛をあて先に設定しARP要求をブロードキャストします.
それに答えるのはISDN ルータAのみですので問題なくMACアドレスを得ることができます. ルータAのみですので問題なくMACアドレスを得ることができます.
しかし,ここでクライアントAの設定を以前のままにしていた場合,
すなわち8ビットのサブネットアドレスを設定し忘れた場合はどうなるでしょう.
クライアントAのネットワークアドレスは172.16.0.0./16となります.
サブサーバ172.16.1.200にARP要求を送るとなると,
それは同じネットワーク上に存在するマシンだと判断し,
172.16.1.200をあて先に設定しARP要求をブロードキャストします.
ここで初めてプロキシARPが出てきます.
ネットワーク部の異なるLANでのARP要求に応じるのがプロキシARPです.
参照 Cisco Systems, Inc/プロキシ ARP
プロキシARPはあて先IPアドレスが"自分宛ではない"ARP要求に対し,
自分のところに持ってくればよいと代理で答えます.
この動作を行う ルータは上図では[ ルータは上図では[ ルータ]と[ISDN ルータ]と[ISDN ルータA]の2つになります. ルータA]の2つになります.
これが2つの応答があった理由だと考えます.
すなわち,
クライアントのサブネットアドレス設定変更をし忘れたため(27)
この理由だと「同一セグメントで正常に接続できるものもあった」という本文も納得
がいきます.
|
(Tomの解答例)
クライアントのサブネットアドレス設定変更をし忘れたため(27)
|