テクニカルエンジニア(ネットワーク)過去出題問題平成7年 午後2 問2最終更新日 2004/01/24
|
| Tomのネットワーク勉強ノート |
| |
| |
| |
問2
フレームリレー方式を利用したネットワークの再構築に関する記述を読んで 設問1~5
に答えよ。
S社はシステムインテグレーションを行っている会社である。現在S社ではOA機器のレン
タル第務を営むP社のシステム構築プロジェクトを手掛けている。このプロジェクトにおけ
るS社の業務受託範囲は、レンタル業務システムの再構築に関する要求定義から基本設計ま
でである。S社のU君(入社5年目)は、このプロジェクトにネットワーク担当者として参
加することになった。U君は過去のプロジェクトでネットワークの設計を中心に実務を行っ
てきたが、今回のプロジェクトでは要求定義から基本設計までの工程においてサブリーダを
務めることとなった。
次の資料1、2は、このプロジェクトに参加するに当たって渡されたP社の業務概要と、
現行のレンタル業務システムに関する事前調査の資料である。
【資料1:P社の業務概要】
P社はOA機器のレンタル会社で、コピー機やパソコンなどを個人及び企業にレンタル
している。東京に本社、全国に8支社があり、地域ごとに営業活動を行っている。顧客
は会員制になっていて、現在約45万会員が登録されている。このうちの約5万会員にレ
ンタルしている。各地域ごとの会員数は表1のとおりである。レンタル物件は東京本社、
大阪支社、名古屋支社の倉庸に保管されており、顧客のレンタル要求に応じていったん
最寄りの支社に配送された後に顧客に届けられる。
表1地域ごとの会員数
単位:人
| 地域 | 北海道 | 東北 | 関東 | 東海 | 北陸 | 近畿 | 四国 | 中国 | 九州 |
| 本社・支社 | 札幌支社 | 盛岡支社 | 東京本社 | 名古屋支社 | 金沢支社 | 大阪支社 | 高松支社 | 広島支社 | 福岡支社 |
| 会員数 | 19,000 | 15,000 | 195,000 | 67,000 | 10,000 | 87,000 | 10,000 | 22,000 | 25,000 |
【資料2:レンタル業務システムについて】
P社のレンタル業務システムは次の三つの管理システムからなっていて、図1に示す
東京本社のホスト計算機(ホスト)で運用されている。
(1)レンタル会員管理システム
レンタル会員の入会登録、退会処理を行う。会員データベース(DB)は東京本社の
ホストにあり、本社及び各支社の端末で入出力処理を行う。
(2)レンタル物件在庫管理システム
レンタル物件の追加と削除、貸出・在庫状況を管理する。ホストに倉庸ごとの物件
DBをもち、レンタル会員管理システムと同じ端末で入出力処理を行う。
(3)請求管理システム
会員のレンタル状況を管理し、日次請求処理をバッチプログラムで実行する。月次
処理として、月額利用料金の請求書を作成する。東京本社経理課の端末だけで入力処
理を行う。本社・支社の端末からは入金状況などの確認ができる。
一日の業務終了後に、新しく増えた会員の情報や物件のレンタル情報を請求DBに反
映する。
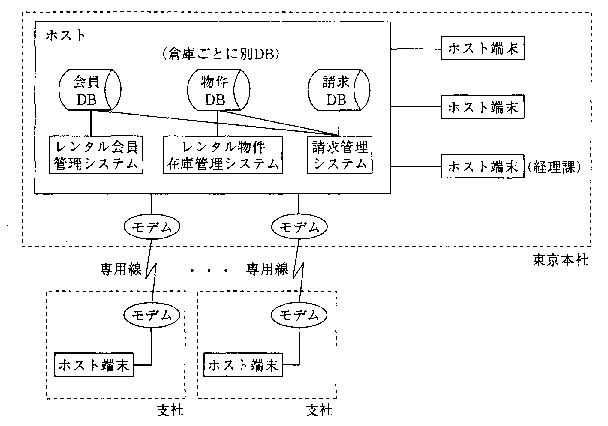
図1 レンタル業務システムの構成(現状)
本社・支社の端末はホスト接続専用の端末(ホスト端末)で、キャラクタだけを表示
できる。ホストと各支社のホスト端末は9,600ビット/秒の専用線で接続されており、
プロトコルはHDLC手順である。ホスト端末は、本社に3台、各支社に1台ある。
ホスト端末には業務メニューが表示され、メニューに従って利用者が入出力操作を行
う。ホスト端末は通常、電源を入れたままになっている。支社では業務オペレーション
を行うだけで、システムの保守ができる人はいない。
【システム再構築の背景】
今回、システムを再構築することになったのは、次のような背景からである。
最近レンタルの業務量が急速に増大した。そのため、物件在庫の確認や、貸出業務の
入力を頻繁に行う必要があるが、現状のシステムでは各支社のホスト端末が1台だけな
ので、業務の処理能力が限られている。ホスト端末を増やす案が検討されたが、トラン
ザクションの増加によって応答性が悪くなるため、現在東京に集中している処理を見直
して支社にデータベースを置き、レンタル会員管理システムを分散処理化することにし
た。
更に、他社との競争上、次のような要望もあげられた。
(1)各支社で、会員の利用実績を参考に、その地域に特化した視点でデータを編集し、
ダイレクトメールなどを使った積極的なセールスを行いたい。
(2)新規購入したレンタル物件のカタログを作成し、各支社に配付するのに時間がかか
るため、オンラインカタログを実現したい。すなわち、写真などのイメージ情報を含
めたレンタル物件の仕様を端末から見られるようにしたい。
【要求定義フェーズ】
新システムのデータ処理の要求は、次のように定義されている。
(1)レンタル会員管理システム
① 自支社分の会員DBだけをワークステーション(WS)にもち、会員DBのフォー
マットは全国共通とする。
② WSごとに、会員DBをもとに地域情報を加えて二次加工した独自のDBをもつ。
③1日に1回WSが自動的にジョブを起動し、会員DB(共通フォーマットのもの)
をホストへ転送する。会員DBを参照する請求管理システムのバッチプログラムを
翌朝の6時までに終わらせるために、ホストへの転送は業務終了時刻の午後10時か
ら始めて翌朝の午前3時までに完了する必要がある。
(2)レンタル物件在庫管理システム
物件DBはこれまでどおりにホストに置き、本社・支社からオンラインでアクセスす
る。物件データには写真を含むイメージデータを付加する。1件の処理につき、端末か
らホストヘ256バイトの問合せデータ、ホストから端末へ8×10^3バイトの物件データの
伝送がある。物件データのネットワーク上の伝送時間は5秒以内に抑える。
(3)請求管理システム
このシステムは現在とほぼ同じで、会員DB、物件DBを参照する部分の修正を行う。
【新システムの構成】
新システムの構成を図2に示す。東京本社のホストはこれまでどおり残し、本社と各
支社にレンタル会員管理システム用のサーバ(ワークステーション)を設置する。本
社・支社ともに端末としてパソコンを設置し、LANで接続する。なお、現在のシステム
で使用中のホスト端末は、リース契約満了まで(1年以上あり)は請求管理システム用
として使用する。
本社と各支社を接続する回線は、コストの面からできるだけ1本に集約したい。移行
手順はまず、基幹ネットワークを新しく構築する。ホスト端末を9,600ビット/秒の専用
線から基幹ネットワークに移行する。そして新システムを約3か月間テスト稼働する。
新システムのテストが完了したら本番稼働を開始する。
U君はデータ処理の要求定義に基づいて、ネットワークの基本設計に必要な要件を四
つに分類し、調査内容を加えて次のような基本設計の要件調査表にまとめた。
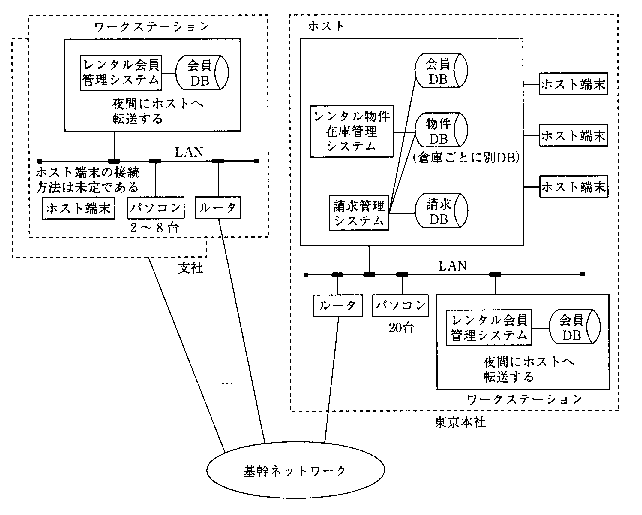
図2 新レンタル業務システムの構成
表2 ネットワーク基本設計の要件調査表
| 要件 | 設計のための調査事項 | |
| 1 | 業務処理の明確化 | アプリケーションの実行される場所や人出カの場所の調査 |
| 2 | [ ] | [ ] |
| 3 | [ ] | [ ] |
| 4 | [ ] | [ ] |
【基本設計フェーズ】
U君は、先にまとめた要求定義項目表をもとに関連する情報を集めた。また、基幹ネ
ットワークに関しては高速ディジタル回線の代替案としてフレームリレー方式を検討す
ることになり、Y社のサービス仕様書、ルータの機器仕様書を入手した。そして、基本
設計の基硬資料として次の五つの資料にまとめた。
・トラフィック分析表
レンタル物件在庫管理システムの問合せ件数と会員DBの夜間転送のデータ量を調べ、
3年後までの伸びを考慮して設計目標値を定めた。
・ネットワーク導入・運用要求
ネットワークの導入・運用に関する要求をP社の運用担当者からヒアリングした。
・Y社フレームリレーサービス仕様書
Y社(特別第二種電気通信事業者)のサービス仕様書からネットワーク設計に必要な
項目を抜粋した。
・採用候補ルータ一覧表
今回使用する予定のルータのネットワークヘの接続性を検討するため、機器仕様書か
ら抜粋した。
・移行手順書
本番移行までのネットワーク利用方法をまとめた。
次に各資料の内容を示す。
1.トラフィック分析表
表3 各支社からのレンタル物件在庫管理システムの問合せ件数(3年後)
単位:件/時間
| 大阪支社 | 名古屋支社 | その他各支社(1支社当たり) |
| 160 | 80 | 32 |
数字はピーク時1時間の問合せ件数
表4 支社から夜間転送される会員DBの量(3年後)
単位:10^6バイト
| 大阪支社 | 名古屋支社 | その他各支社(1支社当たり) |
| 80 | 50 | 20 |
2.ネットワーク導入・運用要求
次の7項目について、P社の東京本社のシステム部が中心となって運用・管理を行
う。
(1)導入管理
現在の本社、各支社のオフィススペースの中でLANを新設する。LANやWANの管理
は本社で一元的にとりまとめて行う。
(2)構成管理
ハードウェア 、ネットワーク、ソフトウェアを対象とする。
(3)データ管理・セキュリティ管理
データ及びソフトウェアの配付・管理、データを含めたシステムのセキュリティ管理
を行う。
(4)稼働実績管理
システムの稼働状況を管理する。
(5)障害管理
障害に対する対応、対策を行う。
(6)ネットワークオペレーション
ネットワークシステムのオペレーション方法を整理し、
明確にする。
(7)教育訓練
エンドユーザの教育訓練を行う。
3.Y社フレームリレーサービス仕様書(Y社パンフレットから抜粋)
| (1)フレームリレー仕様 接続論理インタフェース:フレームリレープロトコル 物理インタフェース:Ⅰインタフェース DLCI制限:32まで CIRの制限:物理回線速度の1/4以上 物理回線速度以下 接続形態:PVC(相手固定接続)だけ可能 (2)月額料金表
注 b/s:ビット/秒
注 b/s:ビット/秒 |
4.採用候補ルータ一覧表
表5 採用候補ルータ一覧表
| A型 | B型 | |
| パケット処理能力 | 60,000パケット/秒 | 15,000パケット/秒 |
| ITU-T V.35、Ⅰインタフェース 最大4回線 |
ITU-T V.35、Ⅰインタフェース 最大2回線 |
|
| 768kビット/秒まで | 128kビット/秒まで | |
| LANプロトコル | TCP/IP | TCP/IP |
| |
PPP:Point to PointProtocol
5.移行手順書
(1)基幹ネットワークを開通させる。基幹ネットワークは高速ディジタル回線又はY社フ
レームリレーのいずれで構成するか未定であるが、各支社のLANとはルータを介して
接続する。
(2)本社・支社のLANを構築し、ホスト端末を9,600ビット/秒の専用線からLAN経由に
よる接続に切り替える。そのためには【 a 】が必要となる。【 a 】の実現方法とし
て【 b 】する方法がある。
(3)新システムのテストを行う。
U君は、P社のネットワークの基本設計を、次のような方針のもとに進めることにした。
(1)ネットワークの導入・運用要求については、表6に示す中項目に分けて検討する。
(2)ネットワークの構成は、東京本社を中心としたスター形のトポロジとし、ルータを介
して接続する。
(3)回線は高速ディジタル回線かY社のフレームリレーサービスを使う。
(4)Y社のフレームリレーサービスを利用する場合、ISDNを使って回線のバックアップ
を行う。方法として、次の二つが考えられる。
(方法A)
東京本社と各支社のルータの間をISDNで接続してバックアップを行う。
(方法B)
東京本社・各支社のルータとY社のノード間をISDNでバックアップする。
(5)ルータとしては、東京本社はA型、各支社はB型を採用する。
表6 ネットワーク導入・運用要求検討表
| 導入・運用要求項目 | 中 項 目 | 内 容 |
| (1)導入管理 | フロアレイアウト | (ア) |
| 機器選定 | (イ) | |
| 導入スケジユーリング | (ウ) | |
| 導入テスト | (エ) | |
| (2)構成管理 | ハードウェア管理 | ネットワーク構成図、LAN構成図、フロアレイ アウト図及び機器一覧表を作成し、管理する。 |
| ソフトウェア管理 | ソフトウエア一覧表を作成する。 一覧表ではバージョンも管理する。 |
|
| アドレス(ネーミング)管理 | アドレス規則、命名規則を文書化し、決定手 続や責任者を明確にする。 |
|
| (3)データ管理・ セキュリティ管理 |
デリバリ管理 | WS・パソコン上のアプリケーションについて配 布の方法・手順を管理する。 |
| バックアップ管理 | OS、アプリケーション、データのバックアップ方 法を検討し・手順書を作成する。 |
|
| ネットワークセキュリティ | ネットワーク上を流れるデータの暗号化につい て検討する。 |
|
| アクセス管理 | アクセス権の設定、パスワードの管理の責任 者を明確にし、手順書を作成する。 |
|
| (4)稼働実績管理 | |
管理基準を作成し、ディスク・CPUの稼働率 の報告方法を決定する。 |
| ネットワーク管理 | 管理基準を作成し、ネットワークの使用率、応 答時間の報告方法を決定する。 |
|
| (5)障害管理 | 窓口業務 | (オ) |
| 障害対策 | (カ) | |
| 障害履歴管理 | (キ) | |
| (6)ネットワークオベレー ション |
スケジューリング | (ク) |
| 計画停止対応 | (ケ) | |
| 日常オペレーション | (コ) | |
| (7)教育訓練 | マニュアルの整備 | 業務手順を明確にして、ネットワークの機器に 関するエンドユーザ向けマニュアルを整備し、 配付する。 |
| エンドユーザ訓練 | ネットワーク機器の障害時の操作などについて は、計画的に障害訓練を実施し、連絡体制や 手順を確認する。 |
設問1
U君が作成したネットワーク基本設計の要件調査表(表2)の2~4について、要件
をそれぞれ15字以内で記し、設計のための調査事項をそれぞれ35字以内で述べよ。
設問2
本文中の移行手順書の空欄a、bを埋めよ。aは10字以内、bは30字以内で述べよ。
設問3
ネットワーク導入・運用要求検討表(表6)の項目(1)、(5)、(6)について、検討すべき
内容(ア)~(コ)を、それぞれ40字以内で述べよ。
設問4
基本設計フェーズにおいて、U君に代わって次の項目を検討せよ。
(1)基幹ネットワークとして高速ディジタル回線を使って東京本社からスター形に接続
する場合の月額回線料金を求めよ。回線速度は本文中の条件から決定し、決定した理
由を70字以内で述べよ。なお、回線の伝送効率は0.8とする。回線速度の決定のため
には、一つの支社で同時に使える端末は1台として計算すること。
(2)Y社のフレームリレーサービスを採用した場合の月額回線料金を求めたい。札幌、
名古屋、大阪支社についてCIR、アクセス回線速度及びフレームリレーサービス料を
求めよ。なお、フレームリレーサービス料は支社のアクセス回線料及び東京と各支社
間のフレームリレーサービス料の合計とする。また、CIRを決定した理由について、
東京本社~札幌支社、名古屋支社、大阪支社の3区間のそれぞれにつき速度決定の対
象となった業務を挙げ、最低限必要な速度を求めよ。なお、本社、支社はいずれもY
社のアクセスポイントから15km以内とする。
(3)ルータの構成について専用回線方式とフレームリレー方式を比較した場合に、フレ
ームリレー方式が有利な点を25字以内で述べよ。
設問5
P社の基幹ネットワークの障害時のバックアップ方法である方法Aと方法Bについて、
その特徴をそれぞれ70字以内で述べよ。
あなたが採用すべきと考える方法を挙げ、理由を60字以内で述べよ。
| Tomのネットワーク勉強ノート |
| |
| |
| |