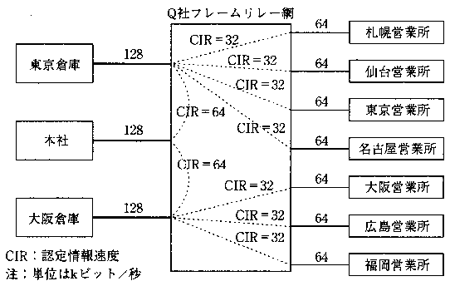|
iTAC塾講義ノート
|
コース名
|
テクニカルエンジニア(ネットワーク)塾Sコース10回目(大阪)
|
講師
|
みずおか先生
|
日時
|
2000年7月2日
10:00~17:00
|
場所
|
クレオ大阪東
|
内容
|
過去問対策2 |
(概要)
今回の講義は、過去問題対策に2回目です。
まず、先日行われました大阪実習の補習として、 スイッチングHUBのワイヤスピードについて触れ、 スイッチングHUBのワイヤスピードについて触れ、
その後から、過去の問題(今回は平成9年 午後1 問5 午後2
問2 リンクはこちら)を解きながら、ネットワーク技術と共に試験技術を勉強しました。
以下にその内容をまとめます。
前回の実習で触れた、 スイッチングHUBのワイヤスピードについて、勉強しましょう。 スイッチングHUBのワイヤスピードについて、勉強しましょう。
 スイッチングHUBの価格は安いものから高いものまでいろいろあります。 スイッチングHUBの価格は安いものから高いものまでいろいろあります。
この価格差は何でしょう?
 スイッチングHUBの選び方の判断基準として、価格のほかに、 スイッチングHUBの選び方の判断基準として、価格のほかに、
・ワイヤスピード
・ポート数
・パケットバッファサイズ(製品に公表されていません)
・フロー制御
があります。
☆☆☆ ワイヤスピード ☆☆☆
ワイヤスピードは過去問題でも出ています。(平成11年
午後2 問2 )
そこには、1台当たりのワイヤスピード 148,810ppsの数値も出ていますので、覚えておきましょう。
ワイヤスピードとは、一般的には最大パケット転送能力のことで、pps(パケット/秒)で表します。
☆☆☆
設問4の類題・・・1台当たりのワイヤスピード
148,810ppsの導出 ☆☆☆
ケーブル 100BASE-Tx(100Mbps)を使用するとします。
1ビットを送るには何秒掛かるでしょう?
→ 1 / (100 ×10^-6) = 0.01マイクロ秒
IPパケットの最小フレーム長は64バイトです。その時のフレーム構成は
| 転送時間 |
0.64μs |
5.12μs |
0.96μs |
|
|
・・・ |
| ビット換算 |
64ビット |
512ビット |
96ビット |
|
|
・・・ |
| |
8バイト |
64バイト |
12バイト |
8バイト |
64バイト |
・・・ |
| |
プリアンブル |
フレーム |
フレーム間隔※ |
プリアンブル |
フレーム |
・・・ |
※フレーム間隔・・・CSMA/CDでは、連続転送できません。
つまり、100Mbpsでの1パケットの転送時間は、
0.64μs+5.12μs+0.96μs = 6.72μs
1秒間での転送パケット数はその逆数なので、
1/ (6.72 × 10^-6) = 148,810 (パケット / 秒)
となります。これが、ワイヤスピードの根拠です。
実習では、 スイッチングHUB(8224XL)を使用しました。 スイッチングHUB(8224XL)を使用しました。
この製品は ワイヤスピード
3.6Mpps、ノンブロッキングです。
これはどういう意味でしょう?
このスイッチは24ポートありました。
最悪、繋がっているPC全てが148,810ppsデータを送ったらどうなるでしょう?
148,810 × 24 = 3.571Mpps
スイッチでこれだけのデータをさばく事が出来れば、待たすことはないです。
8224XLスイッチのワイヤスピードは3.6Mppsです。
待たす(ブロックする)必要がないのでノンブロッキングといいます。
逆にこの数値より小さいと、待ちが出てくるのでこれをブロッキングといいます。
☆☆☆ パケットバッファサイズ
☆☆☆
ブリッジはたいていストア&フォワードです。
そのストアはどこにするんでしょう?
このメモリのことをパケットバッファと言い、大きさをパケットバッファサイズと言います。
このパケットバッファはそう大きくはありません。1ポート当たり512とか1024バイトです。(公表はされてません)
では一杯になったらどうなるでしょうか?
→ 一杯になっても送り続けます。
☆☆☆
フロー制御(バックプレッシャー) ☆☆☆
上で書きましたように、スイッチのパケットバッファがもし一杯になってもデータは送られつづけます。
このために何らかのフロー制御をして上げなければなりません。
これがバックプレッシャーという制御方法で、ブリッジからあえて「衝突しましたよ」とジャム信号を出します。
問題本文へのリンク
設問1
本文中の[ a] ~[ d ]を、それぞれ15字以内の適切な字句で埋めよ。
・用語:全体でのウエイトは小さい。用語の問題を見て、全体をイメージしないように。
わからなくてもショックを受けるな!です。
a:はデータリンク層なので、ブリッジですよね。
b:は制御フレーム、データを持たないフレーム、RIPなどのフレーム・・・。
15字以内なので分からなくてもうまくごまかしましょう。
c:認証なので、PPPですね。
d:PPPはデータリンク層ですね。
本文中に出てくるマルチプロトコルの意味
PPPの上はIPでもIPXでもなんでもいいです。
しかし、PPPの元となっているSLIPはIPしかダメです。
なんでもOK・・・マルチプロトコル
です。 |
(解答)
[a]=ブリッジ [b]=制御フレーム [c] =
PPP [d]=データリンク
設問2
本社と支店間のISDNサービスの“通信料金削減”のために、LAN間接続機器がもつ
べき機能を二つ挙げ、それぞれ20字以内で述べよ(ただし、”回線自動切断機能”は除
くものとする。
|
・何を問われてるかをしっかり確認しましょう。(何を問われているかにマーキング!)
機能を問われています。
ISDNは専用線ではありません。従量制料金なので使えば使うほどお金が掛かります。
従量制料金を安くする方法は大きく2つあります。
・回数を減らす・・・フィルタリング機能(無駄なパケットを流さない)
・時間を減らす・・・データ圧縮、通信速度の向上
あと、深夜料金(テレホーダイ)を使うなどありますので、間違いでなければ使ってもいいでしょう。
本文の図中のL(LAN間接続機器)はブリッジかルータですのでアドレス管理しています。
→フィルタリング機能が使えます。
時間を減らす方法は、ISDNなら通信速度は変えられません。データ圧縮は使えます。
よって答えは、フィルタリングとデータ圧縮でいいでしょう。
|
(解答)
・フィルタリング
・データ圧縮
設問3
図2に示すE社の新ネットワークに関する、次の小問に答えよ。
(1)データ伝送の終了時点から回線切断までの無通信時間の監視タイマ値として、30秒
と5秒の2案を検討する。設定値が30秒(案1)と5秒(案2)の両案の月額通信料
金を、大阪及び横浜のそれぞれの支店ごとに計算せよ。
ただし、通信料金の算出には、付表5の各種使用料は含めないものとする。
・計算問題は本題の数値にマーク!
・本社には50名、各支店にはそれぞれ10名の営業担当者
・受注データの1日分をまとめて毎日18時に支店から本社ヘアッブロード
・翌朝9時に各支店から接続してダウンロード
・Bチャネル1本を使用
・接続要求は、2~5分に1回程度
・検索サービスは平日の8~18時
| 支店 |
1接続当たりの
通信時間(秒) |
1日当たりの
接続回数(回) |
1ヶ月当たりの
運用日数(日) |
| 大阪 |
40 |
200 |
20 |
| 横浜 |
20 |
250 |
20 |
・30秒(案1)と5秒(案2)の両案の月額通信料金を計算
☆ 無通信時間 ☆
例えば、1秒間データを送って、またその3秒後にもう一度1秒間データを送るケースを考えましょう。
この場合、データを送り終えたので通信を切り、再び確立するので20円掛かります。
それでは不経済なので、通信を終えても、しばらくの間データが来ないか監視して、
次のデータが来なかったら切るようにしています。この時間のことを無通信時間といいます。
| |
案1 設定値 30秒 |
案2 設定値 5秒 |
| 大阪 |
|
|
| 横浜 |
|
|
料金計算をするうえで、この無通信時間の中で次の通信が来るか来ないかがポイントとなってきます。
この中で、もっとも通信時間が長いのが大阪の案1で70秒。
・接続要求は、2~5分に1回程度なので、次の通信は来ないと考えられるでしょう。
問題では、月額通信料金を聞いています。
料金計算にはいろいろなものがありますので注意しましょう。
月額使用料ではないので、付表6を使います。(付表5は使いません)
付表6を見てください。
◎モードが3種類あります。
今回はデジタル通信モードBを使用します。
根拠:ISDNサービス(基本インタフエースのディジタル通信モード)を利用したLAN間接続
☆ こういう根拠にもこだわりましょう。 ☆
◎時間帯は昼間
根拠:・検索サービスは平日の8~18時
◎距離 東京~大阪 408km、東京~横浜 29km
(距離はラインマーカーと定規で線を引いて求めることをオススメ)
これにより、大阪は16.5秒で10円、横浜は45秒で10円となる。
☆ 大阪 案1 ☆
↑ 70/16.5 ↑ × 10円 × 200回 × 20日 = 200,000円
☆ 大阪 案2 ☆
↑ 45/16.5 ↑ × 10円 × 200回 × 20日 = 120,000円
☆ 横浜 案1 ☆
↑ 50/45 ↑ × 10円 × 250回 × 20日 = 100,000円
☆ 横浜 案2 ☆
↑ 25/45 ↑ × 10円 × 250回 × 20日 = 50,000円
|
(解答)
大阪 案1 200,000円
大阪 案2 120,000円
横浜 案1 100,000円
横浜 案2 50,000円
(2)(1)の計算結果から、高速ディジタル回線を使用した方が経済的と考えられるのは、
どの支店のどちらの案か。また、その場合の回線速度は幾らか。ただし、通信料金の
算出には巻末付表10の月額使用料のうちの、回線距離の項以外は考慮しないものとす
る。
| |
案1 |
案2 |
| 大阪 |
200,000円 |
120,000円 |
| 横浜 |
100,000円 |
50,000円 |
専用線の通信料金は、
| |
64kbps |
128kbps |
| 大阪 |
169,300円 |
226,700円 |
| 横浜 |
104,000円 |
142,000円 |
大阪の64kbpsの計算式:
↑ (408-240)/20 ↑ × 1,700円 + 154,000円 = 169,300円
大阪の128kbpsの計算式:
↑ (408-240)/20 ↑ × 3,300円 + 197,000円 = 226,700円
よって、大阪の案1より専用線の方が安い。 |
(解答)
大阪 案1
設問4
本社と支店間の通信量と通信頻度の増加に対応するために、ISDNサービスの特徴と
LAN間接続機器のもつ機能を生かして"通信の高速化"を実現したい。この実現策に
関する、次の小問に答えよ。
(1)LAN間接続機器にもたせるべき機能を15字以内で述べよ。また、その概要を30字
以内で述べよ。
|
・何を問われてるかをしっかり確認しましょう。(何を問われているかにマーキング!)
機能とその概要を問われています。
☆ ISDN ☆
ISDNの基本インターフェースは2B+Dです。
しかしこの問題ではBチャネル1本しか使用していません。
Bチャネル2本を使って、物理的には2本ですが論理的には1本(64k+64k=128kbps)
として使用することが出来ます。
このことを、マルチリンクと言います。
ISDNではバルク転送と言います。
|
(解答)
機能:バルク転送(マルチリンクでも可)
概要:Bチャネルを2本使用して、128kbpsとして通信する。(27)
(2)データ伝送の終了時点から回線切断までの無通信時間を5秒に設定して、この機能
を利用した場合の大阪支店の月額通信料金を計算せよ。ここで、通信料金の算出に当
たっての前提は、設問3(1)と同じとする。
|
バルク転送では・・・
↑ 25/16.5 ↑ × 10円 × 200回 × 20日 = 80,000円
Bチャネル2本分なので、
80,000円 × 2本 = 160,000円
(Bチャネル1本の場合:120,000円)
バルク転送は、通信速度は向上するが、経済性は悪化することを頭においておきましょう。 |
(解答) 160,000円
☆☆☆ 午後2対策 ☆☆☆
☆
午後2は推理小説。真相もあればカモフラージュもあり
☆
時間は午後2と比べれば長いですが、それでも短いです。そして奥が深いです。
推理小説と思ってください。真相もありますが、カモフラージュもあります。
簡単♪と思えば騙されています。
☆ 午後2はユーザへのプレゼンテーション ☆
午後1は回答はいやみな上司(知識有り)への報告のようなイメージでした。
午後2はユーザへのプレゼンテーションのようなイメージになります。
そう知識のないユーザ相手に、自分の会社の製品を使っていただけるように説明しましょう。
☆ まず、本文を読んで全体を把握 ☆
午後1では、時間がないので設問から読み始めましたが、午後2では時間があるので
まず本文を読んで全体を把握しましょう。
読みながら、、、
・午後1と同じように、数字をチェック!
・マイナスイメージ(クレームが来た!
実用に耐えれないなど)の所にライン!
をしましょう。数字とマイナスイメージは違う色にしてもいいですね。
出題は、マイナスイメージに対する対処法が多いです。
「こうしたおかげで良くなった」などのプラスな点を書く出題はあまりありません。
☆ 時間配分 ☆
午後2は120分あります。
・問題選択(問1か問2か) 10分
どっちが自分にとって点が取れるかを考えましょう。
配点は設問文の長さに比例するを考えがちですが、
実際は解答の文字数に比例します。
平成9年 午後2 問2では設問4
(4)・・・100文字で解答、(5)・・・130文字で解答。
平成9年 午後2 問3では設問4
(1)(2)(3)でそれぞれ80文字で解答。
ここがキーとなります。このポイントでどこくらい答えられそうですか?
・本文を読む 20分
十分時間を掛けて読みます。(普通に読めば、10分で読み終えます)
その間に数字とか否定的な表現をチェック!
・設問 70分
・チェック 20分
問題本文へのリンク
Aコースでの解説へのリンクADD
00/9/2
チェックした内容
数字
・全国に7か所の営業所と2か所の倉庫
・社員は600名で、そのうち350名が東京の本社に勤務
・本社と倉庫間は48kビット/秒(専用回線)
・営業所と倉庫間は19.2kビット/秒(専用回線)
・2か所の倉庫を中心とするスター型の構成
1受注当たりの
商品コード数 |
総更新処理
時間(秒) |
ローカルサーバ
更新処理時間(秒) |
メインサーバ
更新処理時間(秒) |
| 1 |
10 |
3 |
7 |
| 4 |
19 |
5 |
14 |
| 8 |
33 |
12 |
21 |
1受注当たりの
商品コード数 |
総フレーム数 |
ローカルサーバ間
フレーム数 |
メインサーバ間
フレーム数 |
| 1 |
920 |
626 |
294 |
| 4 |
1,850 |
1,258 |
592 |
| 8 |
2,680 |
1,822 |
858 |
・フレーム長は100バイト
・1受注当たりの商品コード数が4以下のものは約80%を占める
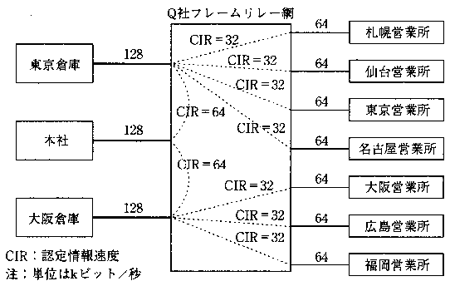
| 項 目 |
仕 様 |
| DLCI制限 |
32まで |
| CIR品目 |
16、32、64、128、192、256、384、512、768kビット/秒、
1Mビット/秒 |
 アクセス回線品目 アクセス回線品目 |
64、128、192、256、384、512、768kビット/秒、1.5Mビット/秒 |
 アクセス回線とCIRの アクセス回線とCIRの
組合せに関する制約 |
一つの アクセス回線に対して、設定可能な一つのCIRは アクセス回線に対して、設定可能な一つのCIRは アクセス回線 アクセス回線
の速度以下であること。
一つの アクセス回線におけるCIRの総和は、 アクセス回線におけるCIRの総和は、 アクセス回線速度の1/4 アクセス回線速度の1/4
以上、2倍以下であること。 |
Q社の提案
・本社、倉庫の アクセス回線速度を128kビット/秒 アクセス回線速度を128kビット/秒
・各営業所の アクセス回線速度を64kビット/秒 アクセス回線速度を64kビット/秒
に変更
・各作業の終了が予定時間より2時間以上遅れた場合は、本部で今後の対応を判断し、ス
ケジュールの見直しを行う
・ICMPエコー要求パケット送信数に対する応答数が、50~60%になってしまう問題
・本社設置の汎用機から各端末あてのポーリングフレームが、常時約30kビット/秒流れていた。
・表4の日程
・本社から札幌営業所ルータヘpingコマンドを発行した場合、100%の応答が確認
・札幌営業所から本社ルータヘpingコマンドを発行した場合も、100%の応答が確認
マイナスイメージな表現
・汎用機の通信プロトコルはルータによるルーティング処理に適合しなかった
・一連のテストで、複数商品の受注入力処理時間に特に大きな問題
・予測された処理時間は、とても実用に耐えられるものではなかった。
・ICMPエコー要求パケット送信数に対する応答数が、50~60%になってしまう問題
・本社設置の汎用機から各端末 あてのポーリングフレームが、常時約30kビット/秒流れていた。
・名古屋営業所のルータの電源を投入し同様なテストを行ったときに、pingコマンド発行に対する応答率が低下する現象が発生
・同機種のルータに交換してテストを実施したが、同じ現象が再現
設問1
オンライン物流システムの総合テスト時の状況に関する、次の小問に答えよ。
ここで、LANでの伝送時間と WAN回線の伝送遅延は無視できるものとし、 WAN回線の伝送遅延は無視できるものとし、 WAN回 WAN回
線での伝送効率は80%とする。計算は表1、2を基に行い、計算結果は小数第1位を四
捨五入して求めよ。
(1)1受注当たりの商品コード数が8のときの、 WAN回線のデータ伝送時間を求めよ。 WAN回線のデータ伝送時間を求めよ。
表1
1受注当たりの
商品コード数 |
総更新処理
時間(秒) |
ローカルサーバ
更新処理時間(秒) |
メインサーバ
更新処理時間(秒) |
| 8 |
33 |
12 |
21 |
表2
1受注当たりの
商品コード数 |
総フレーム数 |
ローカルサーバ間
フレーム数 |
メインサーバ間
フレーム数 |
| 8 |
2,680 |
1,822 |
858 |
 WAN回線のデータ通信時間 WAN回線のデータ通信時間
データ量 / 通信速度 = 858 × 100 × 8 / ( 48 × 10^3 ×
0.8)
= 17.875秒
(フレーム長=100バイト・・・見つけれましたか?)
少数第一位を四捨五入して 18秒
注意:
通信時間は データ量/通信時間です。 覚えましょう。
データ量の
ビット換算(×8)を忘れないようにしましょう。
伝送効率で割るのを忘れないようにしましょう。 |
(解答) 18秒
(2)図2の総合テストを本社の代わりに札幌営業所で行った場合、1受注当たりの商品
コード数が8のときの総更新処理時間を推定する。
表1より、
総更新処理時間は 33秒(本社~東京倉庫間)
では、札幌~東京倉庫では?
(※ここで、>
(c)総更新処理時間を求めよ。を見て,総更新処理時間を計算するための
計算であることをイメージしておきましょう。) |
(a) WAN回線のデータ伝送時間を求めよ。 WAN回線のデータ伝送時間を求めよ。
本社~東京倉庫、札幌~東京倉庫で何が変わるでしょう?
→専用回線通信速度が 48kbps から 19.2kbpsになっています。
通信時間は、
858 × 100 × 8 / ( 19.2 × 10^3 × 0.8) = 44.6875秒
小数第一位で四捨五入して 45秒 |
(解答) 45秒
(b)メインサーバ更新処理時間の中で、 WAN回線のデータ伝送以外に要した時間を WAN回線のデータ伝送以外に要した時間を
求めよ。
メインサーバの処理時間は表1より21秒。
(更新処理時間には、クライアントとサーバ間のフレーム伝送時間も含まれることに注意)
(1)から、フレーム伝送時間は18秒なので、それ以外の時間は、
21-18 = 3秒ですね。 |
(解答) 3秒
(c)総更新処理時間を求めよ。
| ローカルサーバの更新処理時間は12秒のままでいいでしょう。
メインサーバの更新処理時間は 3 + 45 = 48 秒になります。
総更新処理時間は 12 + 48 = 60秒です。 |
(解答) 60秒
※計算問題はストーリー性がありますので、全てを見て流れをとらえて(最終的に何を解くかみて)
(1)から順番に解いていきましょう。 |
設問2
フレームリレー網を利用したネットワーク設計に関する、次の小問に答えよ。
| 補足説明
問題文章では、午後1で"FR網"
午後2では"フレームリレー網"と書かれていました。
出題の中で、書く必要があれば"フレームリレー網"と書きましょう。
・ アクセス回線 アクセス回線
フレームリレー網のアクセスポイントまで アクセス回線を使用する必要があります。 アクセス回線を使用する必要があります。
Q社は アクセス回線に高速デジタル回線(64kbps~1.5Mbpsの各品目)を使いなさいと書いています。 アクセス回線に高速デジタル回線(64kbps~1.5Mbpsの各品目)を使いなさいと書いています。
・DLCI(data link Circuit Connection
identifier) CHANGE 00/9/7
一般回線で例えば3つの方向と通信するには、3本の アクセス回線を契約する必要があります。 アクセス回線を契約する必要があります。
しかし、フレームリレーでは1本契約するだけでよく、アクセスポイントから振り分けてくれます。
どうやるのでしょう?
データの前に識別子(FR網のアドレス)を付けます。この識別子のことをDLCIと言います。
DLCIは5ビットです。(MACアドレスは48ビットでした)。ですから、2^5=32方向まで振り分けることが出来ます。
・通信形態
PVC(Parmanent Virtual Connection)接続です。
・CIR(Circit Committed Information Rate)
CHANGE 00/9/7
FR網はみんなで使っています。
それは高速道路のようなもので、込むこともあります。
速度は0~ アクセス回線まで変化します。 アクセス回線まで変化します。
基準となる速度のことをCIR(高速道路でいう制限速度のようなもの)と言います。
0
CIR  アクセス回線速度 アクセス回線速度
|----------|----------|
重輻輳--輻輳 >|<--正常- >|
↑
とまっている状態
CIRはDLCIごとに設定します。
この設定では、下図の契約は可能でしょうか?
大阪--128kbps--AP--64kbps--東京
|\
32kbps 32kbps
|
\
名古屋 仙台 FR網内はすべて、 アクセス回線速度以下。 アクセス回線速度以下。
FR網のCIRの総和は128kbpsで アクセス回線128kbpsの1/4以上、2倍以下なので可能です。 アクセス回線128kbpsの1/4以上、2倍以下なので可能です。
|
(1)フレームリレー網の伝送容量に余裕がある場合、図3のネットワークで設定された
CIRと実効スループットとの関係を、30字以内で述べよ。
|
・何を問われてるかをしっかり確認しましょう。(何を問われているかにマーキング!)
関係を問われています。
CIRと実効スループットの関係
CIRとは網内が通常状態の時に保証する通信速度のことです。
|
(解答)
CIRは通常状態での実効スループットです。(20)
(2)図3のネットワークで、フレームリレー網が正常な状態の場合でも、必ずしも全フ
レームリレー回線(論理チヤネル)に対してCIRのスループットが維持できない場合
がある。その場合の利用条件を、35字以内で述べよ。
|
・何を問われてるかをしっかり確認しましょう。(何を問われているかにマーキング!)
利用条件を問われています。
本社~東京倉庫の アクセス回線は128kbpsです。 アクセス回線は128kbpsです。
東京倉庫の場合、DLCIのCIRの総和を超えています。
つまり、CIRの総和がその回線の回線速度を超える場合、CIRのスループットは維持できない場合があります。 |
(解答) CIRの総和がその回線の回線速度を超えてる場合。(22)
設問3
IPアドレスの設計に関する、次の小問に答えよ。
(1)P社は図1のネットワークを運用していたとき、各ルータの WAN回線側インタフ WAN回線側インタフ
ェースにもIPアドレスを設定していた。 WAN回線例のネットワークアドレス部のア WAN回線例のネットワークアドレス部のア
ドレスは、全社で幾つあったかを答えよ。
|
・何を問われてるかをしっかり確認しましょう。(何を問われているかにマーキング!)
幾つあったかを問われています。
本社と倉庫間で2本、東京倉庫~営業所間で4本、大阪倉庫~営業所間で3本
合計で9本ですね。 |
(解答)  WAN側・・・9本 WAN側・・・9本
(2)導入したルータの WAN回線側にIPアドレスを設定しないことも可能であるが、設 WAN回線側にIPアドレスを設定しないことも可能であるが、設
定した場合の利点を、35字以内で述べよ。
|
・何を問われてるかをしっかり確認しましょう。(何を問われているかにマーキング!)
利点を問われています。
利点を述べるには相手の欠点を否定すればいい。
A→B 通信できていたのに出来なくなった。どうするか?
IPを設定していなかったら、どのルータで故障したかが分からない。
つまり、障害の切り分けがしにくい。
IPがあったらどうなるか?
pingなどで障害の切り分けが容易になる。
|
(解答)  WAN回線に障害が発生したときに、切り分けが容易になる。(27) WAN回線に障害が発生したときに、切り分けが容易になる。(27)
設問4
あなたの経験に基づいて、フレームリレーへの移行作業に関する、次の小問に答えよ。
あなたの・・・たまに出題されます。
出たら能動的に書いて下さい。
(私は)・・・と思う。・・・と判断する。など。
午後2はこのようにネットワークのReplace(置き換え)やセキュリティ出題されます。
|
(1)表4の[ a ] ~ [ c ]の確認テスト内容を、それぞれ25字以内で述べよ。
| このような移行などのテスト(試験)は近場、隣から、遠くへ、下の層から上の層に行うのが鉄則です。
[ a ]
表4の4 ②で、pingのテストを行っています。pingはICMP(第3層の上位プロトコル)の命令です。
・・・ってことは、3までに第3層までの試験を終えておく必要あります。
表4の2では物理的なことをしています。
ってことは、3はデータリンク層をしなければなりません。
今回のデータリンク層はフレームリレー網です。
表4の3 ③ LMIの補足説明
LMI(Local Management Interface)・・・PVCの状態確認のための機能のことです。
ちゃんと名古屋とつながってるかな?東京とは大丈夫かな?
[ b ]
表4の4(2)で倉庫ルータ経由の本社~営業所のテストをしています。
テストの鉄則は場所については近場から・・・です。
解答として「本社~倉庫ルータ間」と書きたくなりますが、それでは営業所が不完全です。
ここでは倉庫ルータと各拠点間と回答するのがいいでしょう。
[ c ]
表4の4でネットワーク層のテスト、6でアプリケーション層のテストを行っています。
ということは、5ではトランスポート層、セション層、プレゼンテーション層のどれかになります。
そして、5の中でサーバへの接続確認をやっています。
ですから、
セションの要求のテスト
TCPコネクション確立テスト
サーバとクライアントのテスト
のどれかでいけます。
|
(解答)
[ a ] フレームリレー網
[ b ] 倉庫ルータと各拠点間
[ c ]
セションの要求のテスト
TCPコネクション確立テスト
サーバとクライアントのテスト
など
(2)表4の番号2(2)ルータ設定変更作業時、ルータの設定間違いを避けるために実施す
べきチェック方法を、60字以内で述べよ。
|
・何を問われてるかをしっかり確認しましょう。(何を問われているかにマーキング!)
チェック方法を問われています。
あなただったら・・・なので正確な答えはありません。自分の考えを書きましょう。
ルータの設定ですのでルーティングテーブルの設定などです。
RIPテーブルを作った時のことを思い出して下さい。
あれだけの量で内容は一台一台違います。
問題では、設定方法ではなくチェック方法を聞いています。
(不要なことは考えない)
<大前提>(こういうことを頭において解答を考えましょう)
・各ルータで同じものはない。
・設定は大変だ。
・自分の目では見れない。
・ネットワークはまだつながっていない。
(リモートではチェックできない)
◎経験なのでドロくさく書きましょう
・設定内容をプリントアウトしてもらってFAXで送ってもらう
・チェック項目を決めておいて報告してもらう
・電話で読み合わせてチェックする。
今なら・・・
・モバイルのE-mailを使用するのもいいですね。
など書ける答えはいっぱいあります。
|
(解答)
・各ルータで設定された内容をプリントアウトし、それをFAXにて送信してもらってチェックする。(44)
・チェック項目をあらかじめ、相手側のルータ担当の人と決めておいて、チェック結果を報告してもらう。(46)
・ルーティングテーブルの内容を相手に電話で読み上げてもらってチェックする。(35)
・リモートを使ってチェックが出来ないので、ルーティングの情報をモバイルのE-mailを使って転送してもらい、チェックする(59)
など
(3)表4では、Q社の作業は予定では9時45分で終了するにもかかわらず、SI業者の要
求で最後まで残ることになった。その理由を、35字以内で述べよ。
|
・何を問われてるかをしっかり確認しましょう。(何を問われているかにマーキング!)
理由を問われています。
Q社の人はなぜ帰らなかったのでしょう?
さみしいから?
不安だから?
他の人への遠慮?
P社への配慮?
も実際あるでしょう。
しかし、それでは答えにならないので答えを考えて行きましょう。
Q社ってどんな会社?
・通信事業者。フレームリレーなどのサービスを行っています
・Q社の各アクセスポイント担当者は、回線フレームリレー交換機に接続変更します。
・拠点のQ社の担当者は、持ち込んだTAに回線を接続変更します。
この作業は終わったので帰ってもいいはずです。
実際Q社が9:45に帰っちゃってSI業者だけになったらどうですか?
本題からの伏線・・・
切り換え作業は1月の日曜日
2時間遅れた場合、つまりうまく行かなかった場合月曜からの仕事がどうなりますか?
うまく行かなかった場合は元に戻す必要がある。
それはQ社が担当(残しておこう)
|
(解答)
設定がうまく行かなかった場合、元に戻す必要がある。それはQ社担当だった。(35)
(4)東京倉庫のLANを LANアナライザで調査したところ、汎用機から端末へのポーリ LANアナライザで調査したところ、汎用機から端末へのポーリ
ングフレームが測定された。なぜ、本社のルータを越えてパケットが流れたのか、理
由を100字以内で述べよ。
| 勝敗は設問4 (4)(5)あり!
実際、この時のNSPの試験では、この問題が出来る出来ないで合格不合格の分かれ目になっています。
・何を問われてるかをしっかり確認しましょう。(何を問われているかにマーキング!)
理由を問われています。
(4)
なぜパケットが流れたのか?
汎用機→端末のポーリング(御用聞き)
<本社>
| |
汎用機 |
|
端末 |
|
端末 |
|
ルータ |
~ |
倉庫でパケットを確認 |
| |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
| ・- |
------- |
-- |
----- |
-- |
----- |
-- |
------ |
-・ |
|
本社だけのもののはずがルータから外に流れてしまいました。
汎用機は独自のプロトコル独自プロトコルを使っています。
ルータはIP以外ではブリッジ機能を使うことになっています。
これがおかしいのでしょうか?
そのせいでルータ間で常に48kbps中30kbps流れているのでしょうか?
実際は流れていません(常に流れていればそれこそ問題です)
これが原因と書いた人は×です。(実際試験も不合格でした)
ブリッジはアドレステーブルを見てブリッジするかを決定します。
フレームリレーにしたら流れ出した原因はなんでしょう?
考えられるのは
・出る方のポートにアドレス情報があった
・テーブルに情報がなかった。(ためブロードキャストが流れた)
のどちらかです。
フレームリレーにした時にルータはどうしたでしょう?
ルータを置き換えたのではなくて、設定変更をしました。
設定変更したらリブートします。
アドレステーブルは真っさらになります。
その日は休日で電源が切ってあったので端末のアドレス情報が登録されませんでした。
これによりルータのテーブルに端末の情報が入らず、外にパケットが流れ続けた訳です。
(月曜になって、端末の電源を入れれば流れなくなります。)
ここまで気づいて書けるかどうかが、合格率6%の世界なのです!!
|
(解答)
フレームリレーへ変更の際、ルータの設定変更を行ったため、リブートしアドレス情報がクリアされた。
休日なので端末の電源が入ってなく、アドレステーブルに登録されてないため、ブロードキャストとして外に流れた。(100)
(5)東京倉庫を経由した拠点ルータ間での接続テストで、pingコマンドに関する応答の
欠落が発生した。ルータが処理すべきパケットと処理内容を考慮して、欠落が発生す
る理由を、130字以内で述べよ。
|
・何を問われてるかをしっかり確認しましょう。(何を問われているかにマーキング!)
理由を問われています。
欠落が発生する理由
・ルータが処理すべきパケット
・処理内容
名古屋ルータに入れたら落ちました。
→ポーリングはブロードキャストなのでトラフィックが原因でしょう。
120kbps→150kbpsになったら落ちました。
・東京ルータの障害?
置き換えてもダメでした。
ルータの故障ではない。
ルータを新機種に変えたらOKだった。
つまり、ルーティング処理能力のルータに替えればOKになりました。
ここでいうルーティング処理能力って何でしょう?
扱えるプロトコルが多い(TCP/IPも汎用機のプロトコルもOK)
つまり、ルータが処理すべきパケットは汎用機のプロトコル。処理内容はフィルタリング。
それに原因のトラフィックを織り交ぜて130文字以内でまとめて下さい。 |
(解答)
東京営業所まではpingが確認でき、名古屋営業所で欠落が発生した。
また、ルーティング処理能力の高いルータに交換したら発生しなくなったことから、
ルータが汎用機のプロトコルパケットをフィルタリング出来なかったため
トラフィックが増大したと思われる。(122)
|