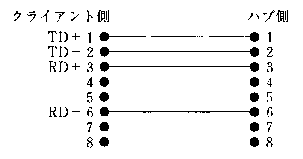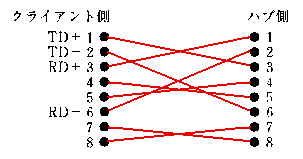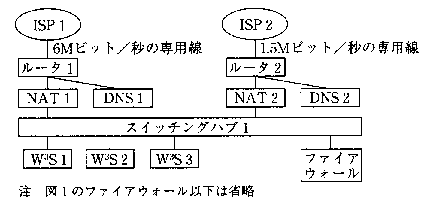問題本文へのリンク
Sコースでの解説へのリンク
設問1
ネットワーク管理システムに関する次の問いに答えよ。
(1)本文中の【 a 】~【 c 】に入れる適切な字句を答えよ。
| aはネットワーク自動構成、ネットワーク自動設定です
bはpingですから、ICMPです。
cは SNMPでいいでしょう。 SNMPでいいでしょう。
☆ SNMPの操作5つ (マスタリングTCP/IP
p.256) SNMPの操作5つ (マスタリングTCP/IP
p.256)
 SNMP SNMP
マネージャー |
|
エージェント |
------------ |
Get-Request
---------------- |
---------→ |
------------ |
Get-Next Request
---------------- |
---------→ |
←---------- |
Get Response
---------------- |
----------- |
------------ |
Set-Request
---------------- |
---------→ |
←---------- |
Trap
---------------- |
----------- |
dはしきい値です。言葉を知らなければ”一定の値”でもいいですが。
eはエージェントです。 |
(解答)
[a]:自動探索
[b]:ICMP
[a]: SNMP
SNMP
[a]:しきい値
[a]:エージェント
(2)R社ではクライアントを障害検知の対象にしていない。その理由を二つ挙げ、それ
ぞれ30字以内で述べよ。
・何を問われてるかをしっかり確認しましょう。(何を問われているかにマーキング!)
理由を問われています。
クライアントをキーワードに探してみましょう。
>省電力化のため、使用していないクライアントの電源は切っている。
これにより、応答なしが、電源を切ってるためか、エラーなのかが分からないですね。
これが一つ目の問題。
>センタと全国に敷か所ある支店間
>大阪支店のクライアント数は、約50台である。
クライアントの数が多い。多くの情報を仕入れる必要がありますから、回線容量が不足します。
|
(解答)
・使用しないクライアントの電源は切っているため(22)
・クライアント数が多く、管理が難しいため(19)
設問2
T君の対応に関する次の問いに答えよ。
(1)どのような接続構成が問題であったのか。問題点を25字以内で述べよ。
・何を問われてるかをしっかり確認しましょう。(何を問われているかにマーキング!)
問題点を問われています。
S氏はどうしたんでしょう?
HUB110に付いてたPCをはずしてHUBを追加しました。
図を書いてみましょう。
| [HUB100] |
| | |
|
| |
| [HUB120] |
|
[HUB110] |
| | |
|
| |
| [HUB121] |
|
[HUB新] |
これを見ればわかりますね。。
HUBの多段接続制限に引っかかってます。 |
(解答)
・HUBの多段接続数が5になり、制限数4を超える点(24)
(2)クライアントをハブに接続するケーブルの結線は図2のようになっている。ハブ同
士を接続する場合の結線を解答欄に図示せよ。
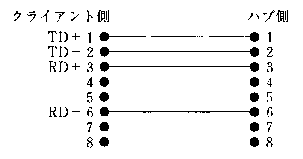
図2 ケーブルの結線状況
| 図示問題です。
これは、クロスとストレートの問題です。
HUB同士の接続ですから、クロスにしてやる必要があります。
使用しているのは1,3と2,6です。4,5、7,8は音声通信のために使用します。 |
(解答)
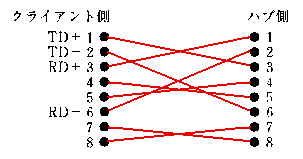
設問3
パケット分析に関する次の問いに答えよ。
(1)収集したパケットから、クライアント1が送受信したものを抽出するには、どのよ
うにすべきかを、30字以内で述べよ。
・何を問われてるかをしっかり確認しましょう。(何を問われているかにマーキング!)
どのようにすべきかを問われています。
クライアント1が送受信したものは、
・送信元又はあて先MACアドレスがクライアント1のもの
もう一つ、
・あて先MACアドレスがブロードキャストのものです。
これを30字以内ってのがつらいんですが、たぶん作問者がブロードキャストを忘れているのでしょう。
”MACアドレス”では無く、IPアドレスと書いてもかまわないんですが、
パケットフィルタリングはレイヤの低いものを収集するのが基本ですので、MACアドレスの方がBetterでしょう。
ARPはIPでは落ちちゃいますよね? |
(解答)
あて先,送信元MACアドレスがクライアント1のものを抽出する。(30)
・・・ブロードキャストについてまで書けないです(字余り)
(2)情報系サーバ、支店サーバのアドレス解決を目的としたARPパケットについて、
記入済の表記に従って表の空欄を埋めよ。
| |
情報系サーバヘのping投入時 |
支店サーバヘのping投入時 |
| ARP要求 |
ARP応答 |
ARP要求 |
ARP応答 |
MAC
ヘッダ |
あて先アドレス |
① |
⑤ |
⑨ |
40-00-00-99-99-99 |
| 送信元アドレス |
② |
⑥ |
⑩ |
40-00-00-22-22-22 |
ARP
メッセージ |
目標IPアドレス |
③ |
⑦ |
⑪ |
172.17.0.101 |
| 送信元IPアドレス |
④ |
⑧ |
⑫ |
172.17.0.1 |
③ ルータの向こう側は別ネットワークです。 ルータの向こう側は別ネットワークです。
MACアドレスを知るためですから、目標IPアドレスは ルータになります → 172.17.0.254 ルータになります → 172.17.0.254
④送信元IPアドレスはクライアント1です。
これにはヒントがありまして、支店サーバへのpingのARP応答を見ると、172.17.0.101になっています。
→ 172.17.0.101
①あて先MACアドレスは?わかりません。分からないから、ARP要求を出しているのです。
ブロードキャスト ff-ff-ff-ff-ff-ff でしたね?
②送信元MACアドレスは、40-00-00-99-99-99です。これも、支店サーバへのpingのARP応答を見れば分かります。
⑥それに対する応答は ルータがしてますから、送信元は40-00-00-AA-AA-AAです。 ルータがしてますから、送信元は40-00-00-AA-AA-AAです。
⑤あて先はクライアントですから、40-00-00-99-99-99。
⑦⑧IPは、いいですね?
支店のときはほとんど同じです。 ⑨要求はブロードキャスト ff-ff-ff-ff-ff-ff です。 ⑪あて先が同一LANのときはターゲットホストに投げつけます。(別LANの時はデフォルトゲートウエイに投げつけます)
ターゲットホストのIPアドレスは172.17.0.1ですね。
|
(解答)
| |
情報系サーバヘのping投入時 |
支店サーバヘのping投入時 |
| ARP要求 |
ARP応答 |
ARP要求 |
ARP応答 |
MAC
ヘッダ |
あて先アドレス |
ff-ff-ff-ff-ff-ff |
40-00-00-99-99-99 |
ff-ff-ff-ff-ff-ff |
40-00-00-99-99-99 |
| 送信元アドレス |
40-00-00-99-99-99 |
40-00-00-AA-AA-AA |
40-00-00-99-99-99 |
40-00-00-22-22-22 |
ARP
メッセージ |
目標IPアドレス |
172.17.0.254 |
172.17.0.101 |
172.17.0.1 |
172.17.0.101 |
| 送信元IPアドレス |
172.17.0.101 |
172.17.0.254 |
172.17.0.101 |
172.17.0.1 |
設問1
本文中の【 a 】~【 j 】に入れる適切な字句又は数値を答えよ。
|
webの負荷分散です。
【 a 】は UPSです。 UPSです。
【 b 】はホスティングの問題です。
W3S1,W3S2,W3S3について、CPU利用率が問題でないW3S1,W3S3は10~20%、
問題のあるW3S2が80~90%で、使える状態ですから、素直に”長くなる”でいいでしょう。
【 c 】の
>CSMA/CDの【
c 】を防ぐため
は、コリジョン、または衝突が入ります。
これはいいですね。
【 d 】~【 f 】
ここの64バイトというのは
Ethernetフレーム全体の最小フレーム長です。
あて先
MACアドレス |
送信元
MACアドレス |
タイプ |
データ |
FCS |
| 6バイト |
6バイト |
2バイト |
46~1500バイト |
4バイト |
| 合計で64バイト~1518バイト |
図 DIX Ethernetフレームフォーマット (マスタリングTCP/IP
P.89)
その前に、プリアンブルとSFD( Start Frame
Delimiter)がきて、
| 7バイト |
1バイト |
|
| プリアンブル |
SFD |
Ethernet Frame |
| 10101010・・・ |
10101011 |
|
101010・・・で、リズムをとって、最後の1011で「はいどうぞ!」って感じです。
【 d 】はプリアンブルですね。
【 e 】と【 f 】は計算問題なんですが、
10Mbpsで64+8=72バイト送る時間ですから、
72×8 / (10×10^6) = 57.6×10^(-6)秒
= 57.6マイクロ秒になります。【 e 】
【 f 】
で、フレーム間隔が9.6μsですから、ギャップ入れてのフレームを出すには、
9.6μs+57.657.6μs=67.2μsになります。
1秒に送れるパケット数は、 1(s)/
67.2(μs/パケット) = 148,880.9パケット/秒になります。
・・・【 f 】
【
g 】 >② ユーザのWWWブラウザは、【 g 】というプロトコルで振分けサーバにアクセスする。 【
g 】は振り分けサーバの方式です。 ブラウザですから、HTTPです。 最後の【h】~【
j 】ですが、、、 表2のアクセス回数を全て足して母数とし、それぞれの範囲について%を求めます。 0以上~1k未満・・・4,398+2,085+1,953+1,719+1,569+1,444=13,168
13,168 / 54,293 = 24.25% >小数第1位を四捨五入した。ですから、24ですね。・・・h
10k以上~100k未満・・・4,073+3,103+2,552+2,132+1,153=13,013
13,013 / 54,293 = 23.9%→24・・・i
1M以上~10M未満・・・1,013
1,013 / 54,293 = 1.8%→2・・・j
|
(解答)
[a]: UPS
UPS
[b]:遅くor悪くなど
[c]:コリジョン、または衝突
[d]:プリアンブル
[e]:57.6
[f]:14,881
[g]:HTTP
[h]:24
[i]:24
[j]:2
設問2
H君は、ネットワークの性能評価に関して上司から指摘を受け、ネットワークに問題
がない理由を考え直した。本来ならばどのように考えるのが正しいか、90字以内で述ベ
よ。
・何を問われてるかをしっかり確認しましょう。(何を問われているかにマーキング!)
本来ならばどのように考えるのが正しいかを問われています。
>“ネットワークの性能については、もっと直感的に判断できるのではないか” と指摘を受けた。
と書いてます。直感的に考えて○だよと言えないか?と聞かれています。
W3S1が10~20%
W3S2が80~90%
W3S3が10~20%
これを見れば分かります。これしかないでしょう。
W3S2のCPU利用率が80~90%と異常に高いのでユーザからクレームが出たんです。
ネットワークはOKと考えていいですよね。
|
(解答)
ネットワークの性能に起因する問題なら、全てのW2Sのユーザからクレームが来るはず。
問題がないのであれば、サーバに問題があるはず。(66)
設問3
振分けサーバ方式に関する次の問いに答えよ。
(1)現行方式から振分けサーバ兼用方式に変えると平均待ち時間はどのようになるかを
述べよ。また、その理由を、現行方式の三つのM/M/1、サーバ振分け兼用方式を
M/M/3の待ち行列モデルに当てはめて100字以内で述べよ。
・何を問われてるかをしっかり確認しましょう。(何を問われているかにマーキング!)
平均待ち時間はどのようになるか、理由を問われています。
今までは、
A社page:W3S1
B社page:W3S2
C社page:W3S2
と決め打ちしています。
振り分けサーバでは、
『CPU利用率をチェックして、いずれかのサーバへ投げつけますよ』
と言っています。
現状は左のマクドナルドのような感じです。
振り分けサーバは右の銀行のような感じです。
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 窓口 |
← |
客 |
客 |
客 |
| |
窓口 |
\ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
\ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 窓口 |
← |
客 |
客 |
客 |
| |
窓口 |
-- |
-- |
客 |
客 |
客 |
客 |
客 |
客 |
客 |
客 |
客 |
|
|
|
|
|
| |
|
|
/ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 窓口 |
← |
客 |
客 |
客 |
| |
窓口 |
/ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3つのM/M/1になります。
マクドナルドはこちら |
|
| |
M/M/3になります。
銀行はこっちです。 |
待ち行列もモデルは、○/○/○/○で表されます。
| ○/ |
○/ |
○/ |
○ |
到着
分布 |
サービス時間
分布 |
窓口数 |
行列の
制限 |
到着分布
D・・・一定間隔
M・・・ランダム
ネットワークの世界ではMになります
サービス時間分布
D・・・一定間隔
M・・・ランダム
こちらはD、M両方あります。
Dはどんな時でしょう?
ATMはセル長が一定ですからDになります。
窓口数
1かnです。
行列の制限
10人以上は並ばせないとか制限がある場合に使いますが、一般には使いません。
設問には
3つのM/M/1と書いています。上の図では、左が3つのM/M/1で、右はM/M/3になります。
この場合、
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| W3S1 |
← |
客 |
客 |
客 |
| |
W3S1 |
\ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
\ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| W3S2 |
← |
客 |
客 |
客 |
| |
W3S2 |
-- |
-- |
[振り分けサーバ] |
客 |
客 |
客 |
客 |
客 |
客 |
客 |
客 |
客 |
|
|
|
|
|
| |
|
|
/ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| W3S3 |
← |
客 |
客 |
客 |
| |
W3S3 |
/ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
振り分けサーバ方式の方が、待ち時間が短いです。これの理由ですが、
待ち行列が存在しているとき、M/M/3では、全ての窓口がサービス中です。
M/M/1 × 3 の場合は、空き窓口ができる場合があります。
|
(解答)
平均待ち時間は短くなる。
待ち行列が存在しているとき、M/M/3では、全ての窓口がサービス中となるが、
M/M/1×3の場合は、空き窓口ができる場合があるため。(80)
(2)CPU使用率の関係が3台のW3S間でどのような状態になっていれば、期待どおり、
負荷の分散が図られたと言えるか。その判断基準を50字以内で述べよ。
| 判定基準といっても、数字がないのですが、主旨はこんな感じです。
→CPU使用率がほぼ等しい
これしか無いでしょう。 |
(解答)
3つのW3SのCPU使用率がばらつきなく、ほぼ等しい(26)
(3)サーバ振分け機能を実現するに当たって、H君は振分けサーバ兼用方式の方が振分
けサーバ専用方式に比べて良いと判断した。その理由を40字以内で述べよ。
・何を問われてるかをしっかり確認しましょう。(何を問われているかにマーキング!)
理由を問われています。
振り分けサーバにも2種類あります。
専用と兼用です。
専用は(振り分けサーバ , Wサービス , Wサービス)
兼用は(振り分けサーバ+Wサービス , Wサービス , Wサービス)
図4と図5を比べればいいですね。
図4(兼用)の方が、均等です。図5(専用)は振り分けサーバのW3S1だけが使用率が低いのがわかります。 |
(解答)
振り分け機能はCPUに負荷があまりかからないので、全体の負荷が分散されない。(38)
設問4
二重化ネットワーク案(図6)で、ISP1の障害や ルータ1、DNS1が故障のとき、ユ
ルータ1、DNS1が故障のとき、ユ
ーザのWWWブラウザからW3S1へのアクセスがなぜISP2経由でできるようになるか。
その動作概要を120字以内で述べよ。ただし、DNSやNATの動作、及びIPアドレスの解
決を含めること。
・何を問われてるかをしっかり確認しましょう。(何を問われているかにマーキング!)
動作概要を問われています。
さらに、DNSやNATの動作、および、IPアドレスの解決も含めることです。
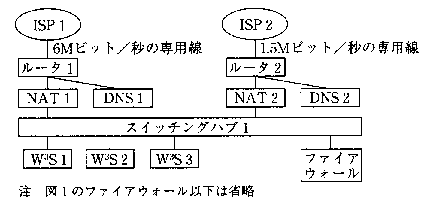
ユーザの指定したURLからあて先WWWサーバのIPアドレスを求めるにはDNSを使います。
DNSはプライマリが使えないと、セカンダリに切り替わります。
WWWサーバのIPアドレスは、グローバルアドレスをNATでプライベートアドレスに切り替えます。
W3Sの内部アドレスをA、W3SのNAT1側公開アドレスをB、W3SのNAT2側公開アドレスをCとしましょう。
>③ NAT (Network Address Translator)は、内部アドレスと公開アドレスの二つ
>の異なるIPアドレスを1対1に対応づける機能をもった装置
と書いてます。テーブルを持っています。
NAT1側はB⇔A、NAT2側はC⇔Aに置き換えます。
DNSにはプライマリDNSでW3S1⇔B、セカンダリDNSでW3S2⇔C
の情報を持っています。
JPNICにはDNS1をプライマリ、DNS2をセカンダリと申請しておきます。
外からつなぐ場合、DNSに聞いて送信します。
DNS1or ルータ1orISP1が壊れました。 ルータ1orISP1が壊れました。
すると、DNS1に達することが出来ません。ですから、DNS2に切り換えると、W3Sの値はCになります。
これをまとめてください。
このまま解答するのは難しいです。
上で書いたように、W3Sの内部アドレスをA、W3SのNAT1側公開アドレスをB、W3SのNAT2側公開アドレスをCと
最初に書いてみましょう。原則は3つ入れることです。
字余りになったら、何がテーマか考えましょう。今回はアドレス解決がテーマです。 |
(解答)
W3Sの内部アドレスをA、W3SのNAT1側公開アドレスをB、W3SのNAT2側公開アドレスをCとする。
正常時はプライマリのDNS1でBを知りBはNAT1でAに変換される。
DNS1への通信が不能時はセカンダリのDNS2に切り替え、Cを知りCはNAT2でAに変換される。(120)
設問5
H君の報告書に対する上司の指摘に関して、次の問いに答えよ。
(1)上司はH君がユーザからのクレーム対策を急ぐあまり、W3S2の性能改善にとらわ
れすぎていないかと指摘しているが、ほかに考えられる問題は何か。100字以内で述
べよ。
・何を問われてるかをしっかり確認しましょう。(何を問われているかにマーキング!)
ほかに考えられる問題を問われています。
他の問題・・・表1にあります。
・W3Sの故障
・ファイルのバックアップ
に対しての対策をしないといけない点
|
(解答)
W3Sの故障や、ファイルのバックアップに対しての対策をしないといけない点。
また、サーバの振り分け後であれば、バックアップの際、同期についても検討しなければならない。(83)
(2)上司は図6に示す二重化ネットワーク案のRシステム運用ガイドラインの見直しを
H君に指示した。障害への対応及び負荷バランスの管理に関して新たに盛り込む事項
は何か。それぞれ40字以内で述べよ。
・何を問われてるかをしっかり確認しましょう。(何を問われているかにマーキング!)
障害への対応に関して新たに盛り込む事項
と
負荷バランスの管理に関して新たに盛り込む事項を問われています。
障害対策と負荷バランスです。
二重化ネットワーク案の障害対策は
>④ISP1は常時使用、ISP2はバックアップ用とする。つまり、ISP1の障害や ルータ1、 ルータ1、
>DNS1が故障の場合は、ISP1からISP2経由に切り替わる。
です。障害時にはISP1からISP2に自動的に切り替わります。
ってことは、これはセットで考えてください。
自動切換えがあれば、自動復旧も必要です。
負荷バランスに関しては、
ISP1,ISP2が常に動いていれば話は別なんですけど、ISP2は死んでいます。
ですから振り分けサーバでしょう。
→振り分けサーバがきちんと動作しているのか?
です。
|
(解答)
・障害対策
障害時のISP1からISP2への自動切換えとともに、自動復旧も盛り込む(35)
・負荷バランス
振り分けサーバがきちんと動作しているのか監視する。(24)
(3)二重化ネットワーク案(図6)と比べ、上司が示したネットワーク負荷分散案(図
7)の長所と短所を、それぞれ40字以内で述べよ。
・何を問われてるかをしっかり確認しましょう。(何を問われているかにマーキング!)
長所と短所を問われています。
図6と図7の比較です。
比較と出たら、いつもの7要素
| |
|
図6 |
図7 |
| 機能性 |
|
|
|
| 運用性 |
管理 |
|
×構成が複雑で、障害時の処理が難しい |
| 性能 |
応答時間
通信速度 |
○専用線が太いので |
|
| 安全性 |
セキュリティ |
|
|
| 信頼性 |
稼働率 |
△
DNS1にたどり着けない時迂回ができる |
△
 スイッチングHUB1が落ちても通信できます スイッチングHUB1が落ちても通信できます |
| 経済性 |
通信料金 |
|
○専用線の通信料金 |
| 拡張性 |
|
|
|
|
(解答)
・長所
○もし、 スイッチングHUB1が故障発生時でも、切り替えることにより通信できる(34)
スイッチングHUB1が故障発生時でも、切り替えることにより通信できる(34)
○ISP1側の専用線の帯域が4.5MHzなので通信料金が安く、経済的である。(37)
・短所
○ISP1側の専用線の帯域が4.5MHzなので通信速度が遅く、性能面で劣る。(36)
○構成が複雑で、障害時の処理が難しい(17)